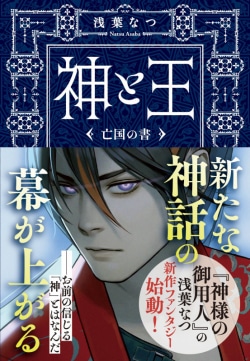◆
――えーと、人参と玉ねぎとー……
――玉ねぎはまだあるよ。
――え、ほんと? じゃああとなんだっけ。
――お肉。
――そうだ、お肉。それくらいかな。
――ヨーグルトは?
――あ、それも!
もう何度も聞いた音声メモを、颯太は飽きずに聞いている。母は買い物リストを音声メモで残す人で、これが最新で最後のメモになった。彼女の使っていたスマートホンは、すでに契約を解除しているが、本体だけは未だ颯太が持ち歩いている。
――えーと、人参と玉ねぎとー……
――玉ねぎはまだあるよ。
――え、ほんと? じゃああとなんだっけ。
画面をタップさえすれば、いつでも母の声は蘇った。去年の自分と会話する聞き慣れた声は、街の喧騒の中でも褪せることがない。
指定された公園のベンチに腰かけて、颯太は右足首をそっと動かす。昨日より随分痛みはましになっていて、歩くだけなら問題ない。骨には異常がないということだから、このまま良くなっていくだろう。
土曜日の昼前、公園には親子連れの姿もある。バドミントンに興じる父子の姿をなんとなく目で追って、颯太は家にいるはずの秀史と倫はどうしているだろうかと考えた。二人でどこか散歩にでも行っただろうか。
「颯太」
ぼんやりと音声メモを繰り返し再生していた颯太は、自分を呼ぶ声に、目が覚めるような感覚で意識を引き戻した。
「久しぶりね!」
目線の先では、母方の祖父母が相好を崩している。こんなふうに笑う人たちだったかなと、颯太は一瞬の間を置いて微笑んだ。この前会ったのはいつだったかと記憶を辿ると、ああ、あの日だったかと、心に僅かな影が差した。
母と母の両親は、昔からそれほど折り合いがよくなかったと記憶している。険悪と言うほどではないが、母は颯太を連れて実家に帰りたがらず、祖父母もこちらを訪ねてくることはなかった。電話をすることも稀で、年に一度、盆暮れ正月のどこかで顔を合わす程度の、そんな関係だった。
颯太を近くにある寿司屋に連れて行った祖父母は、新鮮な海鮮の載ったちらし寿司を勧めた。生魚はあまり得意ではないのだが、颯太は子どもらしく明るく礼を言って箸をつけた。
「最近はどうだ、うまくやってるか?」
日本酒を飲みながら、刺身の盛り合わせを摘まんでいる祖父が、他愛ない会話の途中でそう尋ねた。随分ざっくりした質問だった。
「何か困ってることとかない? だってほら……、あちらは……血も繋がっていないし、ねぇ?」
祖母が遠慮がちに言って、同意を求めるように祖父に目を向ける。
「実の父親でもない男と暮らすのは、苦労するだろう」
杯の酒を飲み干して、祖父は眉間に皺を刻んだまま口にした。
「あのねぇ颯太、お父さんとも相談したんだけど、……うちの養子にならない?」
あまりに唐突な祖母からの誘いに、颯太は思わず箸を持つ手を止めて顔を上げる。
「そうすれば倫くんの面倒も見なくてすむわよ。きっと苦労してるんでしょう?」
どう答えようか迷って、颯太は曖昧な笑みを浮かべた。養子にと誘うなら、今までにも機会はあった。なぜ今なのだろう。あれ以降、ずっと没交渉だったのに。
「颯太は男だし、きちんとした教育を受けるべきだ。うちに来るなら、大学に行かせてやる」
祖父はそう言って、手酌で杯に酒を注ぐ。その隣で、祖母も当然のように微笑んで頷いた。
「……今のところ、困ってることはないし、学校にもちゃんと行ってるよ」
颯太は慎重に言葉を選びながら、知らない外国語を話すようにぎこちなく舌を動かした。
「倫と遊ぶのも楽しいし、秀史も、ごはん、作ってくれるし」
「でも、あちらはお仕事もあるでしょう?」
「倫のお迎えがあるから、ほとんど決まった時間に帰ってくるよ」
「そのために仕事をおろそかにするとは、情けない奴だ」
祖父が鼻で笑うように吐いた言葉が、腐った果実のように嫌な熱を持った。颯太の中で反論したい自分と、それができない自分が、渦を巻いて倦んでいく。
「颯太にとっても悪い話じゃないと思うの」
祖母が取り繕うように言って、媚びるような笑みを向ける。
「返事は今すぐじゃなくていいから、考えてみて。ね?」
颯太は生ぬるい魚の切り身を口に含んだまま、笑顔の形を作って頷いた。
二、
颯太が物心ついたころから、母はいくつかの仕事を掛け持ちしていた。中でも螺子などを作る工場でのパートが主で、三年以上は勤めていたようだ。しかしその工場が、不況のあおりでパートを切ることになり、母も例にもれず解雇となった。最後の給与に少しだけ色は付いたようだが、到底何カ月も暮らせるような額ではない。
「いいのないわねぇ……」
スマートホンで検索したアルバイト募集の画面を覗き込んで、絢子はぼやく。たまたま一緒に解雇になったパート仲間から声をかけてもらって、期間限定の農協のアルバイトには滑り込んだが、出荷時期が終わる頃にはまた仕事がなくなってしまう。それまでに新しい仕事を見つけなければならなかった。
「あやこ、これは?」
まだ漢字の読めない颯太は、絢子が持ち帰った無料求人誌を広げて、適当に時給の高いものを指さした。
「あー、これはだめ。夜に出ないといけないから。昼間に働けるやつがいいの。朝は八時か九時からで、夕方五時くらいまで」
颯太は神妙に頷いて、もう一度誌面に目を走らせ、その時間が書いてあるものを探した。その様子を見て、絢子が小さくため息をついた。
「私が正社員になれれば、それが一番いいのかもしれないけど……。あの時、反対されても大学に行っておけばよかったなぁ」
颯太にはダイガクもセイシャインもよくわからなかったが、いつも明るい母が、今日はやけに落ち込んでいる、というのはよくわかった。
「でもあやこは気が利くし、いつも笑顔だし、大きな声で挨拶してくれるから上等だって、吉村のおばちゃんが言ってたよ」
向かいの家の“吉村のおばちゃん”は、苦言も多く苦手に思っている人も多いようだが、自分たち母子のことはよく気にかけてくれていた。
「吉村さん、そんなこと言ってたの?」
「言ってたよ。若いのに頑張ってるって」
「やったー、褒められちゃった」
絢子はふざけて笑って、颯太の頭をわしわしと撫でた。
「愛想がいいのは昔クラブにいた頃に取った杵柄。でもこれしかできないの」
きねづか? と颯太が問い返したが、絢子はどこか苦みのある顔をする。
「社会でお金を稼ぐには、それだけじゃ難しいのよ」
後日母は、農協で知り合った人に紹介されたという、ファミリーレストランのオープニングスタッフとして働き始めた。大学生もシニアもいるという現場は、毎日刺激的らしく、もともと接客業が得意だったこともあって、楽しそうに通っていたことを颯太は覚えている。
それから半年ほどたったころ、その日は休みだったにもかかわらず、母の働いているファミレスへご飯を食べに行こうと誘われた。目玉焼きの載ったハンバーグが美味しくて、夢中で食べている最中、同じバイト仲間である豊岡秀史と名乗る大学生を紹介された。
その時から予感はあったのだ。
時折視線を交わし合う二人の間には、とても温かな空気が流れていた。
まだ若くて頼りなく、小さい子どもの扱いに慣れない秀史は、颯太とどう接していいかわからずに困っていたが、優しそうな人だということは十分わかった。
何より母が嬉しそうに笑っていることが、颯太にとってはとても重要だったのだ。
(つづく)