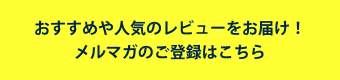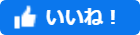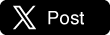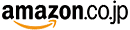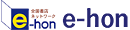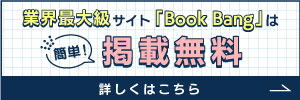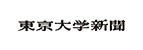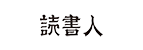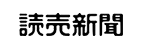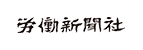河野有理×森本あんり「日本の『反知性主義』を問い直す」尾原宏之『「反・東大」の思想史』刊行記念 後編
[文] 新潮社

河野有理さん(左)と森本あんりさん(右)
欧米や東アジアでは、政治家の高学歴化が進んでおり、エリート意識丸出しの政治に対する反感が国民のあいだで高まっている。ところが日本では、良くも悪くも政治家の高学歴化がそれほど進んでいないという。
いったい、それはなぜなのか――。日本思想史を専門とする河野有理・法政大学教授と、アメリカの反知性主義を研究してきた森本あんり・東京女子大学学長が、新潮選書から刊行された話題書『「反・東大」の思想史』(尾原宏之、新潮選書)を参考に、日本における反知性主義の伝統について対談しました。
***
■日本の知的伝統は「反・科挙」?
河野:日本思想史研究者の尾原宏之さんが刊行した『「反・東大」の思想史』(以下、『反・東大』と表記)という本が話題になっています。エリート養成機関である「東大」に対抗しようとした教育者や思想家を描いた本ですが、これは森本さんが書いた『反知性主義:アメリカが生んだ「熱病」の正体』(2015年刊)の日本版として読めるのではないかと思いました。
森本:アメリカの反知性主義には、「神の前ではみな平等である」というキリスト教的な軸があります。だから、ハーバード大学やプリンストン大学の出身のエリートと対峙しても、一歩も引かない強さがある。もし「反・東大」が日本版の反知性主義だとするなら、何がその思想的な軸となるのでしょうか?
河野:その軸をひと言で説明するのは難しいのですが、私のような日本思想史研究者の目から見ると、日本には明らかに反知性主義の伝統があると感じます。尾原さんの『反・東大』で扱っているのは明治以降の時期ですが、これに江戸時代以前の思想史を補助線として加えると、それが分かりやすくなると思います。
江戸の反知性主義を考える時には、その反対、つまり東アジアの知性主義を考える必要があります。中国大陸そして朝鮮半島、いずれも科挙による能力試験を導入していました。試験に受かった人が権力を握るという制度が社会的に実装されていたわけです。これに対する江戸の社会は世襲の軍人による支配です。
つまり、中国大陸や朝鮮半島が「勉強すれば偉くなれる社会」だったのに対し、江戸の社会はそうではない。江戸時代の人々にとって「勉強し過ぎるのは良くない」というのが普通の感覚であって、むしろ勉強すると人格が悪くなるとさえ思っている(笑)。
森本:そこに「門閥制度は親の敵(かたき)」という福澤諭吉が、『学問のすすめ』を掲げて登場するわけですね。
河野:まさにその通りなんですが、これもまた『反・東大』に大変興味深いエピソードが出てきます。『学問のすすめ』で、勉強ができる者が出世するメリトクラシー的な社会を目指していた福澤が、東大と対抗していく中で、徐々に「反・学問のすすめ」としか呼びようのない主張に転じていく。
森本:ああ、あそこは面白かったですね。貧乏人に高度な教育を与えると、気位が高くなって自らの境遇に不満を抱き、社会の安寧を乱すようになるとか、今の時代からすればとんでもない主張を福澤が始めるんですが、明治日本の強い上昇志向社会を背景に考えれば、理解できるように思います。
河野:東大が創設されて、日本の科挙とも言うべき高等文官試験が行われ、官僚が我が物顔で幅を利かすようになると、「勉強ができるからって、それだけがすべてじゃない!」というメンタリティが出てくる。これは江戸以来の「日本の反知性主義」の逆襲として見ることができるのではないか。
■政治家の学位が低いのはなぜか

『「反・東大」の思想史』尾原宏之[著]、新潮社
森本:そうか! 今でも「勉強だけがすべてじゃない」という考え方はありますが、そのルーツは江戸時代まで遡ると見えてくるのですね。まあ、実際にその台詞が出てくる場面を考えると、確固とした信念というより、勉強嫌いの言い訳みたいに聞こえそうだけど。
河野:よく言われることですが、いまだに日本の政治家の学歴はそう高くない。いや、東大とか慶應とかごろごろいるじゃないかと言われるかもしれません。また『反・東大』のなかではマスコミと並んで政界に人材を多数送り込んだ早稲田のことが扱われていましたが、たしかに早稲田も多そうです。「雄弁会」とか。ただそこで言われているのは専門的には「学校歴」のことで、「学位」という意味での「学歴」ではない。端的に言えば、修士号や博士号を持っている政治家はいまだにごくわずかです。これに対し、たとえば欧州では多くの政治家が当然のように博士号を持っています。
森本:そうなんです。その点では日本はちっとも学歴社会なんかじゃなくて、「教育後進国」です。その一方で、さっき河野さんが言われたように、「だから何なんだ」と開き直る人も多いでしょう(笑)。大学教員の立場からするとやや複雑な気持ちですが、その意味では日本はとても平等な社会と言えるのかもしれません。
河野:おっしゃる通りです。欧州の高学歴の政治家たちが、エリート意識丸出しの政治を行って国民の反感を買っている姿を見ていると、むしろ日本の方がいいんじゃないかとさえ思えてくる(笑)。実際、たとえばヤシャ・モンクのような政治学者は欧米における議員の極端な高学歴化をリベラル・デモクラシーの危機の要因の一つに挙げていますが、その心配は、幸か不幸か、日本にはなさそうです。
いま文科省は博士号取得者を増やしていこうと躍起になっていて、私もそのこと自体は悪い話ではないと思っていますが、はたして反知性主義の土壌がある日本社会で受け入れられるかどうか・・・。
森本:企業の側も、博士号を取った30歳過ぎの人材を採用するよりも、学部を卒業したばかりの若い人材にオン・ザ・ジョブ・トレーニングを施した方がいいという発想が根強くあるように見えますね。