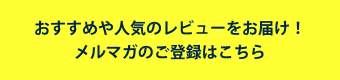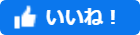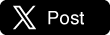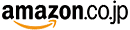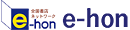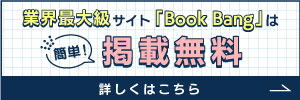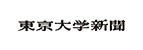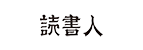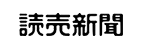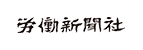『ノイエ・ハイマート』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
距離のもたらす遠さと近さ
[レビュアー] 小池水音(作家)
近親を亡くした二十歳の頃、「アイ・ラブ・ユー」という文について考えた。かけがえのない「ユー」を喪うこと。人は死後においても記憶/記録として残るが、時とともに記憶は薄れ記録は散逸する。「ユー」が損なわれてしまえば、「ラブ」もまた変質を免れえない。あるべき目的語を失った不完全な他動詞となる。そうして残った「アイ」を見ず知らずの他者のように感じてしまうのは、あたりまえのことではないか? そんな言葉遊びを通して、現在地を捉えようとした。「以前」の自分との距離を測ろうとしていた。
「ユー」は住んでいた土地にも、家にも、荷に加えられなかった私物にも置き換えうるだろう。難民と呼ばれる人々はそうした、かけがえのない「ユー」を残して国を出る。旅路においては不完全な「ラブ」ですら捨て置くべき重荷となる。その人たらしめていたほとんどすべてを失った「アイ」は撚り糸が解けるようにして、「難民」の一人になる。
『ノイエ・ハイマート』という風変わりな成り立ちの一冊を背骨のように(しかし緩やかに)貫く一連の小説は、そうした解けかけの「アイ」たちが、いくつもの国境を越える過程を追う。命を分ける岐路に常に立たされる緊張、疲労。物理的な不快や痛み。それぞれの国が見せる冷酷、あるいは温情。過酷な道行きで生じうる厚意や、ささやかでたしかな知恵を読者は垣間みる。
連作は一方で、難民と呼ばれる「アイ」から幾重もの「距離」を取って書かれている。シリア紛争を逃れて西側諸国を目指す多くの「アイ」がいる。その過程を取材するビデオ・ジャーナリストのラヤンがいる。以前にイラクで彼と知り合った同業者の至は、折々でラヤンから送られてくるメールの文章で、その過酷な道行きについて知る――さらに言えば読者は、ラヤンが恐らくは英語で綴った文章を至による日本語の解釈で読んでいる、とも捉えうる。
距離という点に目を向けるとき、連作のあいだに挟まれる小説や詩もまた実にさまざまに描かれている。「彼らは――」「母親は――」として語られる距離の近い三人称の章がある。一人称の「僕」が航空機の貨物庫に潜伏することで国を渡る短篇もあるが、この章は「カフェ・エンゲルベッケンでハムザ・フェラダーが語ったこと」と題されている。「お婆さんと大きな樹」の章はそのまま、難民の子どもたちの言葉を集めた山崎佳代子・山崎光の著作『戦争と子ども』から引用している。二人称の「きみ」に向けて発される詩こそ、あるいは最も密やかな距離を持つ。
小説は多くの場合、実在の距離や時間を無言のうちに取り払い、あまつさえ人物の内心にまで無遠慮に踏みこむことができる。むしろそうした距離、時間を意図的に操作することで、日常の枠をこえた運動を読者に体験させている。しかし、『ノイエ・ハイマート』において章から章へと渡るとき感じたのは、そのような技巧的な操作ではなかった。「ずいぶん迷ったのですけれど、やはりお話ししましょう」とはじまる打ち明け話/然るべき時を経た回想/景色を映すカメラの画面を、さらにべつのカメラを通して垣間みるような迂遠――本著におけるそれらが醸し出すのは、小説が備える非日常の魔力ではない。歩き、手渡し、耳で聞こえる範囲で呼びかけるというような、人が日常で当たり前に行なっている営み、しかしそれが経由に経由を重ねることで、驚くほどの距離を超えて届いたのだという深い実感だった。「難民」を主題とするこの一冊においてその実感は、国を出た人々が歩くべき道のりの途方もなさを、手渡されるものの重みを、耳に届く声の痛ましさを読者に伝えもする。翻って、そうして得た実感が、彼女・彼らの実体験に比したとき、いかに乏しいものであるかも。
SNSは日々遠くの出来事を手元のデバイスへと直線的に届ける。そのことで知る暴力があり、感受できる痛みがある。対抗の術を人々が共有する可能性を生みもする。しかし、彼我のあいだに横たわる距離に裏づけられたこの小説を、いまじぶんは深く求めていたのだと感じる。
距離は常に両義的で、程度が途方もないときには断絶とほとんど同義になる。しかしどれだけ遠くとも誰かの手により脚により声により測られたとき、それは隣接を意味する。「新しい故郷」を意味する本著のタイトルは作中で説明される通り、語義矛盾をはらんでいる。常に過去にあるはずの故郷を、それでも新たに求め「アイ」は歩む。彼女・彼らは一歩ごと、人の渡りうる距離を静かに更新する。歪な文明社会に加担する我々はだからこそ、いまこの瞬間も響く足音に鋭く刺されながらも、その背中に眩しい光をみる。