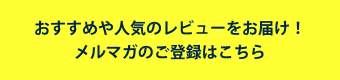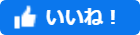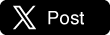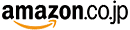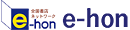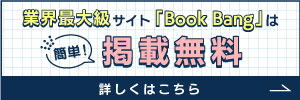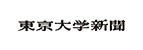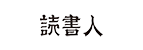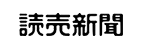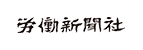『50万語を編む』
- 著者
- 松井 栄一 [著]/佐藤 宏 [編集]
- 出版社
- 小学館
- ジャンル
- 文学/日本文学、評論、随筆、その他
- ISBN
- 9784093891479
- 発売日
- 2024/04/16
- 価格
- 2,420円(税込)
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『50万語を編む 「日国」松井栄一の記憶』松井栄一著/佐藤宏編
[レビュアー] 橋本五郎(読売新聞特別編集委員)
辞書作り3代「用例こそ命」
「辞書」「辞典」と聞けば、すぐ思い浮かぶ光景がある。後に文化勲章を受章する作家、井伏鱒二が帰省した実家で母親に諭されるシーンである。
「ますじ。お前、東京で小説を書いとるさうなが、何を見て書いとるんか。…字引も引かねばならんの。字を間違はんやうに書かんといけんが。字を間違つたら、さつぱりぢやの」
鱒二にとっても範となるべき辞書を編むとはどういうことだろう。気の遠くなるような作業に違いない。この書は、祖父、父、孫が3代にわたり、50年近くもの間、国語辞典という名の高峰に挑んだ歴史と気概の記録である。
著者の祖父松井簡治は約30年かけて、『大日本国語辞典』(全4巻、冨山房)を編んだ。収めた言葉は約20万項目に及ぶ。孫の栄一が15年かけて作った『日本国語大辞典』(全20巻、小学館)は45万項目、75万用例に上り、その第二版では50万項目、100万用例に増えた。後者は「日国」の愛称で親しまれている。
3代にわたって一貫していたのはどういう使い方をされたのかという用例こそが「辞書のいのち」という信念だった。辞書とは単なる言葉の説明ではない。過去の文献にあるものは出典を示し、普段の生活経験に基づいたものは使用例を挙げていくことを心がけた。
そうすると、明治末までは天国は「てんこく」、青空は「あをそら」、無人島は「ムニントウ」と読んでいたことがわかる。「全然面白い」という表現は間違っていると言われることが多い。しかし全然は元々「何から何まで残りなくすべて」の意味であり、肯定にも否定にも使われる言葉だったこともわかる。
簡治が文献を集めて作った索引は40万語だった。しかし、これでは一生かけても完成できない。1年300日専心するとして20年で6000日。収録を20万語に絞れば、1日33語やれば実現できる。そう考えて朝3時に起き、勤めに行く前の8時まで机に向かったという。命をすり減らして創り上げた辞書。大事に使わなければバチがあたってしまう。(小学館、2420円)