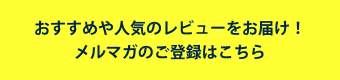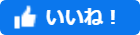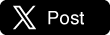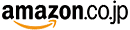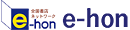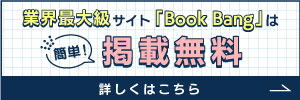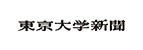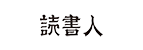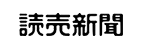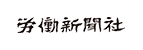『哄う合戦屋』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
現代にも通ずる「異能の天才の光と影」を描いた大ヒット戦国エンターテインメント復刊!
[レビュアー] 細谷正充(文芸評論家)
面白いエンターテインメント・ノベルは、何度でも甦る。その証拠のひとつが本書である。何がどう甦るのかは後で触れるとして、まず作者の経歴から始めたい。
北沢秋は、東京大学工学部卒。会社員生活を経て、二〇〇九年十月、本書『哄う合戦屋』を双葉社から刊行して作家デビューした。刊行に至る事情が、作家のエージェント「アップルシード・エージェンシー」の文芸部の公式noteに書かれているので引用させていただこう。
「そんな北沢さんのデビューのきっかけは、弊社の原稿のスクリーニングにご応募いただいたことでした。当時、社外審査委員であり、かつては河出書房新社の文芸誌『文藝』で編集長をつとめた長田洋一氏が、『哄う合戦屋』の原型となった応募原稿を絶賛。その好評を受けて弊社から双葉社に紹介したところ、すぐに出版が決まりました」
ということである。なるほど、そういう経緯だったのか。当時、いきなり本書が刊行され、しかもメチャクチャ面白い戦国小説だったので、いったい作者は何者だと思ったものだ。
本書は大きな評判を呼んだが、作者の執筆ペースは悠々たるものであった。二〇一一年に『奔る合戦屋』、翌一二年に『翔る合戦屋』と「合戦屋」シリーズを上梓。さらに二〇一五年に『吉祥寺物語 こもれびの夏』、翌一六年に『ふたり天下』(文庫化に際して『天下奪回 黒田長政と結城秀康』と改題)を上梓。実は二〇二四年二月現在、この五作しか作品が出版されてないのだ(他に、細雪純がコミカライズした『哄う合戦屋』が二冊ある)。正直、もっといっぱい書いてもらいたいものだ。
という愚痴はさておき、本書のことである。単行本も売れたが、二〇一一年に文庫化されると、こちらも売れた。しかし現在の出版業界と書店業界の状況では、夏目漱石や芥川龍之介のように、文庫本が常に書店に置かれることは稀である。書店に物理的な限界があり、大量に文庫が出版される現状に対応しきれないのだ。したがって大いに売れた作品でも、いつの間にか絶版(現在は品切れということが多いが、実質絶版である)になってしまうのである。残念なことである。
だが嬉しいことに、真に優れたエンターテインメント・ノベルは、一定のサイクルを経て復刊される。元の出版社からの場合もあれば、違う出版社の場合もある。きっと、かつて作品を読んだ編集者が、物語の面白さを忘れられず、自分の手で復刊したいと思うのだろう。本書を読んでいただければ、たしかにこれは復刊したくなると分かってもらえるはずだ。
そろそろ内容に踏み込むことにする。天文十八年(一五四九年)、甲斐の武田と越後の長尾(上杉)に挟まれた中信濃は、土豪が群雄割拠していた。そこに現れたのが、武勇に優れ、軍略の才も抜群な石堂一徹だ。横山郷を治める遠藤吉弘の娘・若菜と出会った一徹は、吉弘の館に招かれる。かつて村上義清に仕え、二千石を扶持されていた一徹。だが、なぜか一人の主君に長く仕えることができない。誰に仕えても、一度は重用されながら、二、三年で暇を出されてしまうのである。巨体の持ち主で精悍な風貌だが、他人に一線を引いている一徹に、微妙な不安を覚えながらも、自分に仕えるという言葉に喜ぶ吉弘。一徹の働きにより、周囲の土豪を平らげ、領土を拡大していく。しかし一方で、時代の先を行くかのような一徹の組織的な戦いが、家中の反発を買う。そして吉弘の不安が膨らんでいき、事態は思いもよらぬ方向に転がっていくのだった。
信濃では知らぬ者なき才能の持ち主でありながら、従者の鈴木六蔵と馬を連れて放浪している石堂一徹とは何者なのか。横山郷に攻めてきた高橋広家を倒し、逆に相手の城を落とす最初の戦いから、一徹の武勇と軍略が活写される。情報を大切にすることや、兵を軍隊として動かすなど、彼の才能は時代から突出している。織田信長に匹敵するといってもいいだろう。そんな一徹の活躍により、遠藤家が一端の戦国大名に成りあがっていく過程に、戦国小説ならではの楽しみがあった。
だが一徹のキャラクターが、ストーリーに陰影を与える。才能がありすぎるゆえの弊害か、旧来の思考しかできない人を批判し、軋轢を生んでしまう。また、断片的に語られる過去によれば、武田方に妻子を殺されたとのことだ。
そんな一徹だが、芸術にも詳しく、感受性も強い。たとえば若菜という名前が、『源氏物語』から採られていることに、すぐ気づく。若菜の描いた絵の限界を、自ら彫った白木の童女像によって、彼女に悟らせる。主に若菜との交誼を通じて、主人公の人間性の柔らかな部分が、露わになっていくのである。魅力的な女性だが、どこか時代からはみ出しており、だからこそ一徹を理解できる若菜の視点により、孤高にならざるを得ない男の肖像が表現されているのだ。
そういえば、シリーズ第二弾『奔る合戦屋』が刊行されたときの「ダ・ヴィンチ」の記事で作者は、
「あまりにも才が突出しているゆえに、周囲から孤立し、主君からそねまれていく。つまり一徹という男は、僕がサラリーマン生活の中で出会った、才能はあるんだけれど人間関係が上手く作れなくて自滅していった“勿体ない異能の男達”の投影でもあるんですよね」
と語っている。作者は、サラリーマン時代に出会った人々を踏まえ、戦の天才の光と影を、骨太なストーリーの中で描き切ったのである。
さらに、一徹が仕える遠藤吉弘も見逃せない。一徹や若菜だけでなく、彼も作者の創作である。内政には長けているが、勢力の急速な拡大に戸惑い、一徹に怖れを感じる。武田と長尾が伸張する時代の、信濃の土豪を、リアルに描いているのだ。大きな史実の中で、架空の戦国史を創り上げ、多数の人物を躍動させた、作者の手腕は新人離れしている。これほど面白いのだから、本書が復刊されるのは当然のことなのである。
ところで本書のラストを読んで、あらためてタイトルを思い出した人も多いだろう。哄うの“哄”は、どよめき・どよめくの他に、大勢が一斉に笑うことも意味する。その才能によって、周囲をどよめかした一徹は、物語の最後の笑いによって、大勢の読者の胸を打つのだ。なるほど、内容とリンクした、考え抜かれたタイトルだと感心してしまった。
それと同時に読者の中には、このラストからどのようにシリーズを続けるのか、気になった人もいるだろう。第二弾『奔る合戦屋』は時代を遡り、村上義清に仕えていた若き日の一徹が描かれている。本書で触れられていた過去のことなどが、現在に至る一徹の人格がいかに形成されたのか分かるようになっている。そして完結篇となる第三弾『翔る合戦屋』は、完全に本書の続きとなっており、一徹の新たな戦いを扱っている。本書の気になる人間関係についても、きちんと決着を迎えているのだ。こちらの二冊も復刊される予定なので、ぜひとも手に取ってもらいたい。大望に突き動かされた石堂一徹の行き着く先を、見届けてほしいのである。