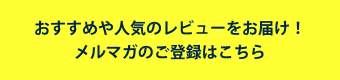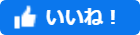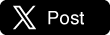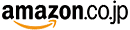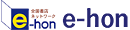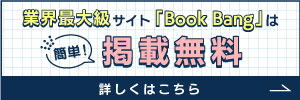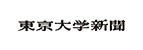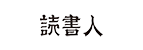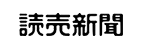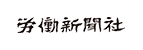『南原 繁 「戦争」経験の政治学』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
『南原繁 「戦争」経験の政治学』川口雄一著
[レビュアー] 苅部直(政治学者・東京大教授)
戦後改革と「理性の共同体」
政治哲学者、南原繁は、高校の日本史教科書では、サンフランシスコ講和会議にむけて、東西両陣営の当事国と講和条約を結ぶべきだと説いた、全面講和論の提唱者として登場する。終戦直後に大学改革をはじめとする教育改革を主導したこと、日本の政治学の再出発にあたって影響力をもった丸山眞男の師であったことも、よく語られる。
だが、その思想の全体に関しては、よくわからないところの多い人物でもあった。主著『国家と宗教』や晩年に刊行した『政治哲学序説』は、ある意味で読みにくい書物である。その元になった諸論文や講義がいかなる論争状況のなかで生まれ、どういう主張がこめられているのか。著書の完成版では記述が時にそぎ落とされ、改訂されているので、その点を十分に理解できないのである。
本書で川口雄一は、形成過程を詳しくたどることで、南原の政治思想の諸側面を、より深く、明晰(めいせき)に分析することに成功した。政治は非合理的なものを排除した、人間の理性の営みである。それが南原が初期から提唱した立場であったが、一九三〇年代なかば、「ロマン的な生の非合理性の要求」に根ざす政治構想を、ナチズムのイデオローグを信奉する学者や、「日本精神」の教化を進める政府が荒々しく提示する。
これに対して南原は「政治上の合理主義」の立場を打ち出して、理性に導かれた「国民共同体」における、立憲制を伴ったデモクラシーの価値を説いた。これが戦後改革をへて独自の「共同体民主主義」の構想へと発展する。それは大学改革を通じて、多くの国民の「教養」の充実を要請するものでもあった。この構想に対応して、天皇と日本神話の意義を説明し直すところも興味ぶかい。
しかし他面で、戦争賛美とも見えるような、戦時中の南原の短歌に見える揺らぎも、川口は指摘する。戦後憲法の非武装規定を南原が支持するようになったのも、その「贖罪(しょくざい)」意識に由来する側面があるのだろう。まさしく没後五十年を飾るにふさわしい書物である。(北海道大学出版会、8800円)