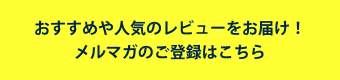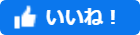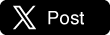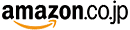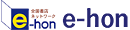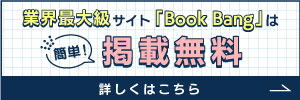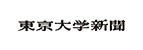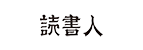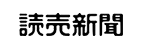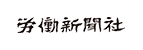『ツユクサナツコの一生』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
魂の救済をめざす傑作
[レビュアー] 中条省平(フランス文学者/学習院大学フランス語圏文化学科教授)

中条省平さん
父と二人で実家に暮らす32歳のナツコは、社会の不平等にモヤモヤし、誰かの些細な一言に考えをめぐらせながら、淡々と漫画を描き続ける。その日常を描いたのが、第28回手塚治虫文化賞短編賞を受賞した『ツユクサナツコの一生』(新潮社)だ。
著者はイラストレーターの益田ミリさん。淡々と日々を送る登場人物たちの何気ないセリフにはっとさせられ、予期せぬ展開に心を揺さぶられる漫画の魅力とは?
朝日新聞で「マンガ時評」の連載をもつフランス文学者の中条省平さんは「マンガの真理を、最も単純に、力強く表現していて、心底感動させられた」と本作を激賞。中条さんによる書評を紹介する。
***
益田ミリの『ツユクサナツコの一生』が今年の手塚治虫文化賞を受賞しました。
受賞した部門は「短編賞」ですが、これは、超大作の多い昨今のマンガのなかでは「短編」に分類されるということでなく、毎回10ページから14ページの「短編」を巧みにつなげて、一個の作品に仕立てあげる手腕の高さが評価されたのでしょう。短編がこつこつと積み上げられた結果、本作は、ひとりの人間の一生を描きだす驚くべき傑作になっています。
益田ミリの短編マンガは、代表作『すーちゃん』に見られるように、日常生活のささいな事柄を発端にして、ヒロインのああでもないこうでもないという思索と感情の揺れを描き、人生にはいいことも悪いこともあるが、それでも生きるに値するとして、読む人にささやかな、しかし確かな励ましを与えてくれるものです。
『ツユクサナツコの一生』もこうした基本路線に変わりはないのですが、その道をさらに一歩進んで、人はなぜ生まれ、生き、死ぬのかという、哲学的ともいえる問いを投げかけています。
そもそも、ヒロインのツユクサナツコという名前について、作品冒頭のエピグラフに、「ツユクサ…朝咲いて昼にはしぼんでしまう、はかない花」という説明が書かれています。これは、誰しも、生まれても結局死んでしまう人間の運命を表したものでしょう。ツユクサナツコという名前そのものが、人生の無常を否応なく感じさせるのです。
じっさい、このマンガの最初の大きな話題は、ヒロインの母親の墓選びです。ここで、彼女が父親と二人きりで暮らしている理由がようやく判明するのです。母親はすでに亡くなっていたわけです。このような繊細な伏線が本書では随所に張りめぐらされています。読みかえすたびにその物語作りの巧緻さに唸らされます。
ところで、ツユクサナツコというのは、ヒロインの本名ではありません。彼女はドーナツ屋でアルバイトをするかたわら、ネットでマンガを発表していて、そのペンネームなのです。本名は橋田というのですが、下の名前は、最初は分かりません。それがいつの間にか分かる仕掛けもじつにうまく、益田ミリはすべてをみごとに計算して描いているのです(作中のマンガに登場する猫の名前まで)。ぜひお見逃しなく。
そんなわけで、この作品は橋田さんのドーナツ屋の仕事と父親との二人暮らしを主に物語るのですが、その現実生活から発想されたツユクサナツコのマンガも同時に掲載していきます。マンガの主人公は、おはぎ屋を経営している春子という若い女性です。つまり、ここには、橋田さんとツユクサナツコとおはぎ屋春子という3人の女性がいて、その人生は微妙に重なり、すこしずつズレているのです。
例えば、橋田さんの母親は亡くなったことが分かりますが、おはぎ屋春子の母親は生きています。それでは、橋田さんはおはぎ屋春子の母親を生かすことで自分の母親の死を贖(あがな)おうとしたのでしょうか? そうかもしれませんが、おはぎ屋春子の母親を描いたツユクサナツコは、「春子の親 出てきたか」と自分でも驚いた様子を見せます。
つまり、ツユクサナツコは、現実の橋田さんの母親から、マンガのおはぎ屋春子の母親を、無意識のうちに、まるで死者を甦らせる霊媒のように呼びだしていたのです。
そのようにして、どうにも動かしがたい現実の人間の生死が、マンガのなかでもうひとつ別の人間の生死となって甦ります。人間はかならず死ぬものですが、芸術(マンガ)のなかで、そして人の記憶のなかで、永遠の生命を得ることができるのです。
芸術(マンガ)とは、そのようにして、死すべき人間の魂を救済し、永遠のなかに置くことのできる手立てです。ツユクサナツコのマンガは、この芸術(マンガ)の真理を、最も単純に、そして力強く表現しています。私はそのことに心底感動させられました。
たとえば、橋田さんはドーナツ屋の常連客だった老人が認知症で記憶をなくすところを目撃します。そして、昔の自分がなくなり、今の自分しかいないとしたら不安だと考えます。
しかし、ツユクサナツコのマンガのなかで、おはぎ屋春子は過去の自分が失われていくとしても、それは仕方のないことだと納得しています。そのようにして、自分が描いたマンガの春子が、自分を失うことに怯えるツユクサナツコを慰めるのです。こんなに繊細微妙な芸術(マンガ)の働きを描きだしたマンガがかつてあったでしょうか? 『ツユクサナツコの一生』は、いわゆる「マンガ家マンガ」のなかでも類例のない一作といえるでしょう。
こうしてささやかに、粘り強く、マンガ(芸術)による魂の救済をめざす本作ですが、ラスト近くで思いがけない展開を迎えます。ネタバレを避けるためにその詳細は明かすことはできませんが、しかし、これまで本稿で語ってきたことが、すべてこの展開の布石として作用していたことを、『ツユクサナツコの一生』を読み終わった方は理解してくださるでしょう。その意味でも、この作品の奥深さに感嘆するほかありません。