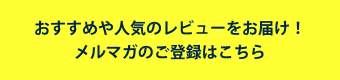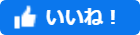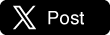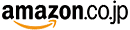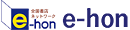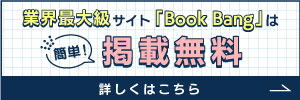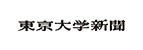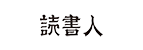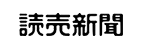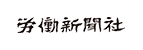『話がうまい人の頭の中』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【毎日書評】話したのに「全然伝わってない!」を減らす2つの習慣
[レビュアー] 印南敦史(作家、書評家)
「うまく話せない」というような悩みは、いつの時代にもある普遍的なもの。どれだけテクノロジーが進化しようとも、私たちのコミュニケーションの土台は「リアルな会話」だからです。
しかも厄介なのは、「うまく話す」ことは難しく、特別な才能が必要であるようにも思えてしまうこと。
けれども『話がうまい人の頭の中』(齋藤孝 著、リベラル新書)の著者は、「うまく話す」ことになんら特別な才能は必要ないのだと断言しています。ちょっとした意識の変化とテクニックだけで、メッセージはみるみる伝わりやすくなるのだと。
本書においてもそのためのポイントを伝えようとしているわけですが、まずは次の2つを知ってほしいのだといいます。
・「話す」と「伝える」は同じではない
・相手が「聞いている」から「伝わっている」とは限らない
(「はじめに」より)
自分が話した内容と、相手が受け取った内容がズレているというケースは珍しいものではありません。ときには、「あれだけいったのに、どうしてわからないんだ!」と怒りたくなる場合もあるでしょう。
こちらは「話した」し、相手も「聞いていた」けれど、結果として「伝わっていなかった」から、そういうことが起きるわけです。しかも認識のズレは、ときに誤解を生み、その誤解がトラブルに発展することも。
でも、話す側に「どういえば相手に間違いなく伝わるだろうか」という意識さえあれば、トラブルも認識のずれも解消できるはず。その意識を常に持っている人こそ、「話がうまい人」だということです。
こうした考え方に基づく本書のなかから、きょうは第3章「話がうまい人が気をつけている3つのこと」に注目してみたいと思います。
「話がうまい人」の指差し確認
話がうまい人と話すと、その人には「特有の考え方」があるのではないか、と感じることが著者にはあるのだそうです。本人が意識しているかどうかは別としても、話しながらいくつかのルールに従って、気を配りながら話しているように思えるというのです。
また著者自身も、ノープランで話し始めることはないのだとか。話し始める前に慎重に、けれども素早く、「なにをいうべきか、なにをいうべきではないか」「どのような表現を用いれば効果的なのか」を、話のなかで組み立てるわけです。
つまり、頭のなかで話の方向性を組み立てて、そこからズレないように気をつけながら話せば、脱線するようなことはないということ。
いわば、話しながら脳内で「指差し確認」をしているようなイメージ。なお、その「指差し確認」のチェック項目としては、次の3つが重要だといいます。
・順番
・タイミング
・リスク
(73ページより)
いうまでもなく、「順番」とは話す順序。あるいは話の組み立て。同じことを話すにしても、どんな順序で話すかによって、伝わりやすさは大きく変わるもの。「いいたいことが伝わらなかった」「誤解された」というような事態を避けるため、「なにを、どんな順序で話すか」をあらかじめ決めておいたほうがいいのです。
「タイミング」とは、「いつ話すか」。すなわち、話しかける頃合いのこと。相手の受け入れる態勢が整っていないとき一方的に話をしても、大事なことは相手の心に届かないはず。話し上手な人は、話す内容もさることながら、タイミングにも気を配っているのです。
「リスク」は、聞き手を不快にさせるような発言ではないか、ということ。SNS上での「炎上」と同じように、話す際にも似たようなことが起こる可能性がある。そのため、気配りをする必要があるという考え方です。(72ページより)
「15秒で伝える」を習慣化する
話をする際には、「まず結論から」伝えるべきだといわれることが少なくありません。「結論→理由/背景/根拠」の順で話をすると、全体の構造がわかりやすくなり、聞き手にも「わかりやすい」という印象を与えることができるからです。
また、結論を先にいう話し方は、話し手にとっても「伝えたいことを確実に話せる」というメリットがあるようです。
たとえば面接の席で、「あなたの強みを20秒程度で話してください」といわれたとします。その際、前置きや前職の職務内容から話し始めたとしたら、結論に行き着く前に「はい、終了!」となってしまう可能性が高まってしまいます。結果として、与えられた時間を無駄話に費やしたことになるのです。
その点、先に自分の長所(=結論)を話しておけば、制限時間が迫ってきてもあわてる必要はありません。
「あとは枝葉の話だから、すべて話せなくても大丈夫」という安心感が精神安定剤のように作用して、余裕を持って話せるようになります。(79ページより)
「面接はあくまでも特別な場面だし、普通は制限時間を設けられることは少ないのでは?」と感じられるかもしれませんが、それは面接のみならず、日常生活にもあてはまること。
話し手(あるいは聞き手)が急に呼び出されたり、第三者から割り込まれたりと、話を中断せざるを得ないシチュエーションは意外とあるものなのです。
「結論から先に話す」は、慣れていない人にとっては難しく感じるかもしれません。
うまくできないと思ったら、日頃からどんな話でも15秒程度で終わらせるように心がけてみてください。
慣れてくれば5秒でも要点くらいは話せるようになるのですが、最初からハードルを上げる必要はないでしょう。(79〜80ページより)
いずれにしても「短時間で話し切る」ということを心がけていれば、自然に無理なく、結論を優先して話せるようになるようです。(78ページより)
本書で紹介されているスキルを活用し、あらゆるコミュニケーションの土台となる「伝わる技術」を身につけてほしいと著者は訴えています。たしかにそうすれば、コミュニケーションに関する苦手意識を解消できそうです。
Source: リベラル新書