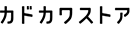『暗い青春』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
青春は暗いものだ。厭世の彼方に希望の光を見いだした、安吾の傑作――『暗い青春』坂口安吾 文庫巻末解説【解説:佐々木 中】
[レビュアー] カドブン
■青春ほど、死の翳を負ひ、死と背中合せな時期はない――。
『暗い青春』坂口安吾
角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。

青春は暗いものだ。厭世の彼方に希望の光を見いだした、安吾の傑作――『暗い青…
■『暗い青春』文庫巻末解説
解説
佐々木 中(哲学者、作家)
安吾は面白い。日本文学、いや世界文学を見渡しても、他に類例を見ない。
しかし、どんなに熱烈な「安吾ファン」でも、安吾の小説、特に長編小説には一定の留保を置く人が多い。曰く、「小説家としては不器用である」「『巧く』はない」「安吾の本領はエッセイ」「小説がエッセイ的でありエッセイが小説的」「ジャンルを超越」など──このような評言は枚挙に遑がない。が、このことは安吾の文業の価値を少しも減じない。
確かに、安吾は長編小説をものしようとしては失敗し、そのたびに深く失望している。即座に付け加えねばならないが、「長編小説を中心とする文学の体制」はたかだか十九世紀ヨーロッパにしか遡り得ず、すなわちロマン主義以後のものである。日本文藝史上もっとも長い歴史にわたって繁栄し存続し得たのは能と連歌であって、要するに舞踏、音楽、演劇、そして「うた」である。
「小説の時代」は人類史上、存外に短い。その時代の内部にしか通用せぬ「偏見」を普遍と見做してはならない。「長編小説を中心とする文学の体制」のなかで本来小説を書くことが本領ではないにもかかわらず小説を書かざるを得ず、そしてあたら才能を空費した、とは言わずとも「小説」という既定のジャンルにおいていらざる苦慮を強いられた「詩人」「劇作家」「舞踏家」等々は数知れない。本人がそうと気づいていても気づいていなくても、である。坂口安吾は日本近代文学史上そのもっとも目覚ましい一人であるだろう。
安吾は二度、長編小説に志して挫折している。
一度目が京都に一年半滞在して苦しみながら書き上げられた『吹雪物語』である。安吾はこの小説について「そのころ、ちやうど千枚ちかい小説を書き終つたのだが、まつたく不満で、読むに堪へないのであつた。千枚の大量の仕事が、まつたく不満であるときの落胆の暗さは、せつない。二度と立ち上る日を予期できないほど、打ちのめされ、絶望に沈まざるを得なかつた」。「その落胆と焦躁は、文学と絶縁せずにゐられぬ思ひに、人を駆り立てるものである」(「囲碁修業」)と語っている。四年後また回顧して曰く、「美しい物語を書かうとして、『吹雪物語』を書きました」。「思ひもよらぬ結果でした。美しいのは、題だけでした。書き終つた物語は、ただ陰惨で、まつくらで、救ひがなく、作者は呆然とし、絶望しました。『吹雪物語』を読む人は、ただ、悔恨と、咒詛と、疑惑と、絶望と、毒を読みとるにすぎないでせう」(「後記」、『炉辺夜話集』)。そして一九四七年、『吹雪物語』の「再版に際して」では、「この小説は私にとつては、全く悪夢のやうな小説だ」と、「この気取り、思ひあがつた小説」と言い切り、「あの頃、私は、何度も死なうと思つたか知れないのだ。私の才能に絶望した」と言っている。安吾のような批評的知性に恵まれた作家の、このような自省に付け加えるべきことは何もない。
二度目が「にっぽん物語」(のち『火』と改題)の執筆とその頓挫である。一九四八年六月、太宰治の自死直後から安吾は抑鬱症状を呈し、克服のためと称してこの長編小説に専念する。しかし睡眠薬アドルム、覚醒剤ヒロポンおよびゼドリンの大量服用によって精神状態は悪化する。のちに回顧して曰く、「この小説を書きすゝめることが出来ない障碍が行く手にあった。それは京都の言葉であった。第一章の『その二』及び第二章の殆ど全部が、京都が舞台になっているからであった。私も十三年ほど以前に、『吹雪物語』を書いていたとき、京都に一年半滞在していた。それだけに多少の心得はあったが、反面、京都弁のむつかしさも心得ていた」(「わが精神の周囲」)と、京都弁に拘った安吾は京都に向かう。が、「京都へついた私は、まったく船酔いに似て、寒気と吐き気に苦悶し、半死半生のていであった。京都の旅館へついて、そのまゝ正月の一週間をねこんでしまった。体力的に消耗しきって、落武者の如く東京へひきあげたが、この旅行への期待と希望が大きかっただけに、私の落胆は甚大であった」(同)。そして更なる覚醒剤と睡眠薬の服用によって幻聴幻覚を発し狂乱状態になった安吾は、二月末に東京大学神経科に入院し、「持続睡眠療法」(「精神病覚え書」)を受けて一ヶ月余昏睡して回復する。が、この長編は以後書き継がれない。
実はこの間に「古都」という長編小説を構想し、やはり挫折している。これはこの文庫に所収されている同名のエッセイとは別物で、やはり京都を舞台にしたものだ。しかし、なぜ、京都なのだろう。
(精神科医にして翻訳者の中井久夫氏は京都で大学時代を過ごしたにもかかわらずこの街がひどく自分を疲弊させる旨述べている。また作家古井由吉氏は筆者に直接、果たして京都でものが書けるかと問い、日本近代文学において京都生まれ京都育ちの作家がいないことを指摘した。「近代」をどう定義するかが問題にもなろうが、京都という街がいずれの時代までかそのような磁場であったことはありうる。)
しかし、繰り返しになるが以上の失敗は安吾文学の価値を少しも減じない。安吾は「長編小説を中心とする文学の体制」という、ある時代を形成したがやがて過ぎゆくであろう束の間の体制のもとにあってたまさか当を得ないときもあったということに過ぎない。
安吾の魅力、孤独であり淫蕩であり退屈しており時に軽薄に傾きまれに殺伐としているが、しかしなおそれでも一抹の純潔を欠くことは決してなく、上質なヒューモアに満ちている不思議なその散文の魅力は、この文庫に収められた作品たちにも露わだ。
「石の思い」は自らの母が「継娘に殺されようと」していたという事実を淡々と述べて波瀾の幼少期を披瀝する。「二十一」では悟りを開こうとし睡眠四時間の猛勉強をして神経衰弱となり、「暗い青春」では文字通り青春の煩悶と友人の死が明察を交えて描かれ、「二十七歳」では「髪ふりみだしてピストンの連続、ストレート、アッパーカット、スイング、フック、息をきらして影に向かって乱闘している」中原中也との愉快な邂逅をよろこんで矢田津世子との恋愛に苦しみ、「いずこへ」では痴情の縺れと言って何を誇張したことにもならない色恋沙汰が、みずから自身をも突き放したつめたさで述懐され、この続編である「三十歳」で矢田津世子と別れた安吾は、「古都」「居酒屋の聖人」でおのれの失敗する青春のありのままをあたかも笑劇であるかのように語って、「ぐうたら戦記」で巨大な戦争のなかにぽっかり空いた不可思議な空隙のただなかで「マグロを食い焼酎をのみ酔っ払って」いる日々を過ごし、そして「死と影」では絶唱ともいうべき「死んではならぬ、と、考えつづけた。なぜ、死んではならぬか、それがわからぬ」の一行を書く。それにしても、なんという痛々しいまでの「正気」か。なんという「なつかしさ」だろう。
これ以上くだくだしく述べるには及ぶまい。もう本文に当たってくだされば良い。しかし安吾は面白い。長編小説の失敗など些事に過ぎない。もし、これが読者にとってはじめての安吾ならば、私は羨望を感じる。読者の前には「文学のふるさと」「堕落論」「続堕落論」「日本文化私観」という卓抜した批評はいうまでもなく、多種多様な安吾の「読み物」の沃野が広がっているのだから。小説なら「紫大納言」「桜の森の満開の下」「夜長姫と耳男」「戦争と一人の女」正続のみならず、「私は海をだきしめていたい」を忘れてほしくない。まだまだ、「イノチガケ」も「青春論」も「安吾の新日本地理」も、「もう軍備はいらない」も、「明日は天気になれ」もある。
そこに我々は、日本いや世界文学においても類例を見ない一人の作家の姿を見る。と、これは、すでに蛇足であろう。