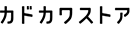人生に躓いたら、この秘密基地に来て。第72回芸術選奨文部科学大臣賞作!――『ムーンライト・イン』中島京子 文庫巻末解説【解説:朝倉かすみ】
レビュー
『ムーンライト・イン』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
人生に躓いたら、この秘密基地に来て。第72回芸術選奨文部科学大臣賞作!――『ムーンライト・イン』中島京子 文庫巻末解説【解説:朝倉かすみ】
[レビュアー] カドブン
■「わかっちゃった。あなたもムーンライト・フリット(夜逃げ)でしょ」。
『ムーンライト・イン』中島京子
角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。

人生に躓いたら、この秘密基地に来て。第72回芸術選奨文部科学大臣賞作!――…
■『ムーンライト・イン』文庫巻末解説
■夢のような
解説
朝倉かすみ(作家)
ページを一枚ずつ繰っていくあいだ、ずっと、感じていたことを書かせてほしい。
筋を追ったり、登場人物たちを知っていったりしながらも、それとはべつに「これってなあに?」とだれにともなくこっそり訊きたくなるような、なんともいえない「感じ」である。
いわば、わたしの感じ方発表会というやつで、のっけから恐縮だ。
いったい「感じ方」などというものは主観によるのだからだいぶ個人差があるくらいのことはわたしだって知っている。おまけにきっと伝えづらい。でも書きたい。本のページをひらいて、言葉を拾っていくなかで、いのいちばんに読み手に起こる働きが「感覚」だと思うからだ。ほとんど生理的な。いっそ好き嫌いといっていいような。
『ムーンライト・イン』の本文がわたしにもたらしたのは、読んでいるのに聞いているような「感じ」だった。
この「感じ」には覚えがあった。記憶を探ると十か十一かそのくらいの時分まで遡る。絵よりも文字の分量の多い本を読み始めたころである。文字のサイズもちいさくなって、色がついているのは表紙だけという、ちょっとおとなっぽい児童書となじみになった。図書室の棚にシリーズで並んでいるのを借りては読んで返したものだ。
わたしらこどもに人気なのは海外の児童文学だった。とりわけて、なんらかのきっかけで主人公が今いる現実世界から、まったくの別世界に迷い込み、入り浸る話である。
わたしらこどもは、わくわくしながらその別世界でのオリジナルなルールを主人公とともにひとつずつ覚えていく。そのうち魔法なんかも使えるようになる。胸が躍るようなできごとや、胸が張り裂けそうなできごとを経験し、もはや別世界の住人になったのかもと思った矢先に大変なことが起こり、のっぴきならない状況に追い込まれる。たいてい魔法はもう使えない。わたしらこどもは主人公とひとつになって、知恵や勇気やアイディアを総動員して立ち向かう。思うぞんぶん活躍し、今いる現実世界に戻ってくるのだが、それはあくまで主人公にとっての現実世界。わたしらこどもは、本を閉じることで、自分らの現実世界に戻ってくる。こちらはこちらで物語という別世界から戻ってくるのだ。
このときも、読んでいるのに聞いているような「感じ」があった。
文字を追うだけで、声が聞こえてくるようだった。黙読しているにもかかわらず、だれかに読んで聞かせてもらっている「感じ」がして、ふしぎだった。
でもまぁそんなもんかと簡単に片付けて、いつのまにか忘れていたのだが、長い長い年月を経て、本作を機に思い出し、考えてみたというわけである。
聞こえていたのは、語り手の声だった。
ここでいう「語り手」は作者ではない。もちろん登場人物でもない。どちらも「語り手」と呼ばれることがあるのでややこしいのだが、『ムーンライト・イン』を例に説明してみる。
この小説は、各章の節ごとに中心となる人物が変わる。節はシーンと言い換えてよく、特定の人物がフィーチャーされる場合が多いが、複数人に次々ピントが合っていく場合もある。そんないくつもの節が車両みたいに繫がって、列車(その名もストーリー号)が走っていくのだが、車両の順番は時系列では決してない。どの車両をどの順番で繫ぐかは作者が決める。むろん、どう書くのかも作者の仕事だ。
(ここで、わたしは、中島さんがプラレールの車両を繫げている絵を想像する。彼女の周りにはレールが渦巻きのように置かれている。巨大な渦巻きだ。なにしろ長めの列車を走らせるので自然とレールも長くなる。中島さんは毎日たったひとりで部屋の真ん中に陣取り、もくもくと車両を繫げていっている──。ちなみにレールの置き方は渦巻きでなくていい。ただし置き場所は平面でなきゃいけない。立体交差はありえない。それは小説が平面──紙でもタブレットでも──に描かれるものだからだ。わたしが中島さんをすごいと思うのは、中島さんの作品は、平面に書いてあるのに、驚くほど立体的ってところである。「わーVRゴーグルを着けたみたいに見えてくるぅ」とか、そういうんじゃない。中島さんの作品を読むと、どの車両を、どう書いて、どう繫ぐかで、物語じたいの奥行きとか幅とか深さとか厚みとか、なんなら風味までだせてしまうことが分かる。これってほんとにほんとにすごいことなんだけど、上手にいえなくて悔しい。まったく、届け、この思いとしか)
話は戻って、「語り手」の件。登場人物は車両に乗っていて、彼らを乗せて繫げて走らせてるのは作者である。わたしがいいたいのは、「あともうひとりいるよね?」ってことだ。なんかいるでしょ、もうひとり。ほら、こういうとこ。Ⅱの五節の最後。
(略)彼がそれを知ることになるのは、もう少し先のことだった。
続く六節の始まり。
ともあれ、拓海が診察室で神妙にしていたころ、マリー・ジョイは市内の別の場所へと車を走らせていた。
いるっぽくないですか? ガイド風の人。読者とコミュニケートするっぽい人。たまにしかでてこないんだけど、でもこの人の声がずっと聞こえてる「感じ」がする。わたしはこの「感じ」がとても好きだ。一種の懐かしさがある。こどものころみたいに、物語の中にどんどん、どんどん、入っていける。
栗田拓海(三十五歳・突然の解雇により無職、自転車旅行中)は夜中、雷雨に遭い、宿を探して廃墟のような駅前エリアを歩き回る。
おいしそうなスープの匂いを漂わせるペンションらしき建物を発見すると、そこにいたのは新堂かおる(八十代・息子夫婦に施設に放り込まれたくなくて家出中)、津田塔子(五十前後・なにかヤバい事件を起こし潜伏中)、マリー・ジョイ(二十代・母国を離れ日本に滞在中)、中林虹之助(七十代・元ペンション「ムーンライト・イン」オーナー)の四人。
拓海は、まるでなにかの一味のような女性三人組からはまったく歓迎されなかったが、オーナーから屋根の修理依頼があり、天候回復まで宿泊できることになる。ところが作業中に骨折。しばしの安静が必要なのだが、住みかを整理して旅に出た彼に帰る場所はない。
〈じゃ、ここにいればいいじゃん〉と言ったのはマリー・ジョイだ。
〈みんな、そうだよお〉と〈非常に説得的な、歌うような抑揚〉で〈あなたもムーンライト・フリットでしょ〉と続けたのだった。
かくして「ムーンライト・フリット(夜逃げ)」した人々の「ムーンライト・イン」での同居生活が始まる。
それぞれの事情や秘密が悩みや憂いとともに少しずつ明らかになっていく。どれもすべてごく個人的なものだ。親子、夫婦の人間関係、老後、自立と依存、性格、恋愛、労働、どれもすべて普遍的なトピックといってよく、そしてどれもすべて現在の日本が抱えている社会問題と絡み合っている。しかもその社会問題が現場の視点で捉えられる。
今いる場所から逃げてきた四人にとって、ちょっと寂れた高原の古い建物での同居生活はたいへんに心地いい。干渉しすぎずに助け合い、そっと気遣い合っている。夢のようだ、とそれぞれが思う。月が満ちていくような、ふくよかな日々である。
わたしらおとなは、読みながら、こういうのいいな、と思うはずだ。まったく夢のようじゃないかと。だけども、だから、わたしらおとなはうっすらかなしい。登場人物らと同じように、こんな夢のような生活がいつまでもつづくわけがないのを知っているからだ。だからこそ夢のような生活にうっとりし、だからこそ、うっすらかなしい、というループが、本を閉じて、現実世界に戻ってきたわたしの胸にまだ繰り返されている。