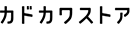『白日』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
組織の論理の中、いかに、人間でいられるか―。 風太郎賞受賞作家の会心作――『白日』月村了衛 文庫巻末解説【解説:永江朗】
[レビュアー] カドブン
■組織の論理に翻弄される中間管理職の苦悩を描いた、波瀾の企業エンタメ!
『白日』月村了衛
角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。

組織の論理の中、いかに、人間でいられるか―。 風太郎賞受賞作家の会心作――…
■『白日』文庫巻末解説
解説
永江 朗(書評家)
月村了衛の作品群の中で『白日』はいささか異色の小説である。現代の日本を舞台に架空の新型兵器が闘う「機龍警察」シリーズのような激しいアクションシーンはないし、実際に起きた事件に着想を得た『欺す衆生』のような犯罪小説でもない。ロッキード疑獄はじめ戦後の政治事件を公安警察の視点で描いた『東京輪舞』とも、記録映画の監督という視点で一九六四年の東京オリンピックと日本社会を描いた『悪の五輪』とも違う。また、『土漠の花』のソマリア、『脱北航路』の北朝鮮、『香港警察東京分室』の香港のように、日本を離れた視点でもない。悪徳クラブの元ホスト2人のその後の人生を描いた『半暮刻』とも違っている。『白日』の舞台は、日本のごく一般的な家庭であり企業だ。
中学3年生の幹夫がビルから転落死する。事故なのか事件なのか。事故だとすれば自殺なのか他殺なのか。ミステリー小説としての『白日』の根幹は、少年の死の真相をつきとめることにある。そこだけ取り出せばシンプルな物語だ。しかし謎を解く探偵役に大手出版社員の秋吉孝輔を据えたことで物語は複雑なものになった。
秋吉が勤める千日出版では、進学塾との合弁で新しい学校を設立するプロジェクトが進行している。それは最新のICTを駆使する通信制の学校で、いじめや不登校に苦しむ生徒の居場所となるだけでなく、高い学力の獲得も掲げる。このプロジェクトを先頭に立って進めているのが局長の梶原。転落死した幹夫の父親である。理想の教育を謳った学校で、その責任者の子供が自殺したとなればスキャンダルになりかねない。
そして、秋吉には幹夫の死の真相を知りたい理由がもうひとつある。かつて秋吉の娘の春菜がいじめから不登校になったとき、優しい言葉をかけてくれたのが幹夫だった。心優しく正義感あふれる幹夫がなぜ死んだのかを秋吉は知りたい。
しかし、真相究明は簡単ではない。立ちはだかるのは会社という組織である。
この設定が実に巧みだ。秋吉が梶原の下で仕事を進めている学校設立事業だが、これは会社の中では傍流の仕事だと目されている。梶原は生え抜きではなく、吸収合併した会社の幹部だった。傍流のさらに傍流なのである。しかもこの会社には社長派と専務派の対立がある。学校を設立するプロジェクトは社長が推している。つまり、プロジェクトが危うくなれば、それは社長の基盤を脅かすと同時に、専務の発言力が増すことにもつながる。幹夫の死は社内の力関係を変える可能性がある。
プロジェクトがうまくいけば、社長派の地位は安泰だろう。しかしプロジェクトが失敗すれば、代わって専務が権力を握ることになるかもしれない。社長派は没落する。秋吉をはじめ社員たちは、社長派につくか専務派につくかという選択を迫られている。
社内で独特のポジションにいるのが人事課長の飴屋だ。変人で「秘密警察」「ゲシュタポ」と陰口を叩かれながら社員たちの行動を見ている。飴屋は専務派ではないかと思われているが、本当のところはわからない。そして、飴屋が何を考えているのかもわからない。不気味な存在だ。
こうしたことは、組織の大小にかかわらず多くの企業や団体でも見られるだろう。派閥とまではいわなくても、なんとなく集団が形成される。複数のボスがいて、ボス同士は対立しがちだ。複数の企業が合併したときなどは、出身企業の違いが対立の原因になる。新規事業への傍流視というのもよく聞く。「あそこは落伍者の吹きだまりだ」などと陰口を叩く。本流にはおもしろくないのである。組織内で互いに監視し合い、就業中だけでなく私生活も含めて日常のあらゆる行為が「得点」と「失点」で評価される。しかも同じ派閥だからといって安心できない。有能な部下が成果を上げることは、上司にとって寝首をかかれる恐怖をもたらす。
そして、その要に人事がある。会社員であれ公務員であれ団体職員であれ、多くの組織人にとって人事は最大の関心事だ。次の異動で誰がどのポストにつくか。ポストは評価の指標であり能力の象徴なのである。以前、大手出版社を辞めてひとりで小さな出版社を立ち上げた人がこんなことを言っていたのを思い出す。「独立して後悔したことはひとつもないけれど、会社帰りに同僚と人事の噂話を肴に飲む機会がなくなったのは寂しい」と彼は笑っていた。人事の噂と愚痴は、組織人にとって最大の娯楽でもあるのだ。
だが、派閥争いも人事も、その組織内だけでの関心事でしかない。まさに「コップの中の嵐」。社長が失脚して専務が後任になろうとも、課長が左遷されようとも、社外の人には関係のない話だ。しょせんコップの中である。『白日』にはその滑稽さがある。
滑稽さを象徴しているのが、『白日』の社員たちにつけられた肩書きだ。この小説にはフルネームを与えられた登場人物と、名字だけの登場人物がいるが、名字だけの人物にも肩書きはつけられている。社長、専務、常務、局長、部長、部長補佐、課長、課長代理、課長補佐。秋吉の取引相手には広報室室長代理とか第二企画部主任という肩書きもある。フルネームよりも肩書きが重要なのだ。
社外の人間にとって肩書きは難解である。専務と常務にどんな違いがあるのだろうか。階級(?)が上なのは専務か、それとも常務か、あるいは同格なのか。代理と補佐の違いもよく分からない。そもそも課長が存在しているのに代理とはどういうことなのか。代理はピンチヒッターではないのか。補佐というのは秘書みたいなものなのか。主任は係長より上なのか。大企業に勤めたことのない人にはほとんど意味不明だろう。どうでもいい肩書きにこだわる人は、町内会の寄り合いとか中学校の同窓会とか公民館の合唱サークルなどで嫌われる。
派閥抗争と肩書き競争は笑えるが、対照的に深刻なのは『白日』の背景にある教育問題である。そもそも新しい学校が必要とされているのは、現代日本の学校が子供たちにとって理想的ではないからだ。
文部科学省が発表した令和四年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、いじめの認知件数は六八万一九四八件。児童生徒千人あたりの認知件数は五三・三件。その内いじめの重大事態は九二三件。「いじめ防止対策推進法」では、重大事態とは「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める」とき、「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」ときと規定している。
子供たちにとって、いじめがこんなにもありふれたものになっていることに愕然とする。学校という空間は子供にとって安心できる居場所ではない。
小中学校における不登校は二九万九〇四八人。高等学校の不登校は六万五七五人、中途退学者が四万三四〇一人。自殺については、文科省の調査(小中高等学校から報告のあった児童生徒数)は四一一人、警察庁の調査では四八五人である。
なお、不登校の要因について、文科省の調査ではいじめによるものを小学校〇・三%、中学校〇・二%としているが、これには識者などから「実態と懸け離れている」という指摘がある(東京新聞二〇二三年十月十九日朝刊)。文科省の令和二年度「不登校児童生徒の実態調査」では、不登校のきっかけを「友達のこと(いやがらせやいじめがあった)」と回答したのは小学生二五・二%、中学生二五・五%にのぼる(サンプル調査)。学校側と当事者である児童生徒側とでは認識に差がある。
肩書きをめぐるコップの中の嵐という大人たちの矮小さと、少年の転落死、崇高な理念を掲げた学校設立の背景にあるいじめや不登校、そして自殺という現実の重さ。『白日』という長編小説が投げかけるものを、われわれ大人はじっくりと考えなければならない。