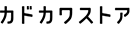『食っちゃ寝て書いて』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
「食う」「寝る」と、もうひとつ大切なこと。――『食っちゃ寝て書いて』小野寺史宜 文庫巻末解説【解説:青木千恵】
[レビュアー] カドブン
■先の見えない時代に自分を信じて歩む、売れない作家と編集者。2人の人生が優しく迫る、再生の物語。
『食っちゃ寝て書いて』小野寺史宜
角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。

「食う」「寝る」と、もうひとつ大切なこと。――『食っちゃ寝て書いて』小野寺…
■『食っちゃ寝て書いて』文庫巻末解説
解説 「書く人」と「読む人」
青木 千恵(書評家)
書く人と、読む人。商品を売る人と、買う人。地下鉄の駅員さんと、乗客。
生活や仕事をする場面、場面で、相手とちがう、「対立項」のような立場になることは多々ある。小説の本=文芸書を作る現場では、書く人と読む人が共に仕事をしている。本書に登場する編集者の井草菜種は、カノジョの石塚彩音に、作家と編集者についてこう説明している。〈編集者と作家で、立場ははっきりしてるから〉、〈やる仕事がちがうってこと。作家は書いて、編集者は読む〉。
本書は、作家の「おれ」横尾成吾と、編集者の「僕」井草菜種を、ダブル主人公にした長編小説だ。物語はとある三月、もうじき五十歳になる作家の横尾成吾が、大手出版社カジカワのベテラン編集者、赤峰桜子から「ボツ」を食らう場面から始まる。赤峰の指示で二度も直したうえでの長編小説のボツは、かなり堪えるものだった。〈書くのと直すのに要した四ヵ月が無駄になるのはキツい。その期間はタダ働き。フリーのつらいところだ〉。横尾とて、すでに著書を十冊以上出している作家だ。「どういうことだ!」「何度も直させといて何だ!」と怒るのもアリな場面だが、横尾は怒らなかった。
あくる四月。カジカワの若手編集者で三十歳になる「僕」井草菜種は、横尾成吾と初めて会う。赤峰が異動し、横尾の新たな担当者になったからだ。ボツ直後の引き継ぎという重い初顔合わせだったが、穏やかな横尾にほっとして、新たな書き下ろしをあらためて依頼する。横尾がボツを食らった三月から、菜種が担当編集者になり、この月に新作小説を刊行しようと定めた翌年の二月まで。本書は先の見えない時代に、作家と編集者それぞれが自分らしい生き方を摑みとっていく一年間のプロセスを、「おれ」と「僕」の視点を代わる代わるにして描いた成長物語である。
「書く人」のほう、作家の横尾成吾は、本書の著者、小野寺史宜さんを彷彿させる造形だ。二年で会社をやめて、二十四歳のときに小説を書きだした。十三年続いた〈投稿暗黒時代〉を送ってようやくデビューしたが、ヒット作は一作だけで順風満帆とは言えない。それでもずっと書き続けている。そんな来歴や、毎朝三~四時台に目が覚めるとバターロール二個とお茶一杯の朝食をとって、いきなり執筆に入る日常のディテールなどは、小野寺さんの実際にかなり近い。肌感覚を大切にして、自分の肌に近いところで書く小野寺さんは、自分に引きつけて作家の横尾を造形したと言えるだろう。
一方の「読む人」、編集者の井草菜種については、どのように造形されているのか、私には分からない。というのも、一口に編集者といっても、その実は十人十色だからだ。作家の横尾は小野寺さんを彷彿させるが、編集者の菜種のほうは、この物語が形づくられるなかで立ち上がってきた「想像上の人物」と言えるだろう。普段から接している職業の人だからこそ深く描かれ、作中作のような仕掛けや、終盤には意外な展開がある。できるだけリアルに引きつけた私小説的な横尾と、想像上の人物である菜種が、共に一人称視点の主となり、奇数月は横尾、偶数月は菜種と作家と編集者のどちらにも偏らず、分量も対等にして物語が成立している。この構成の妙は、さりげなくもこの小説の「すごさ」だと思う。〈人と人の関係は、いつだって一対一。それ以外はないとおれは思ってる〉横尾が、編集者の菜種と「対」になる。二人が共有した一年間を、対等に分け合って生まれた物語なのである。
五十歳の横尾と三十歳の菜種は、年齢も経歴も立場もまったくちがうが、実は「共通項」がある。それは、「もがく人」である点だ。〈ああ。横尾さんは停滞気味だから、ここらで花を咲かせてくれよ。横尾さんに花を咲かせて、ついでに菜種自身も咲いちゃってくれよ〉と、上司の北里耕編集長から発破をかけられて、菜種は横尾の担当になった。つまり、横尾も菜種も〈停滞気味〉だと、社会から見られているのだ。開業医の長男に生まれたが医学部を全部落ち、学生時代にのめり込んだボクシングでプロになれずにカジカワに入社した菜種は、文芸図書編集部に属して丸四年。〈そろそろ何かはっきりした実績を挙げなければと、正直、あせっている〉
作家や編集者には、ライセンスなんてない。プロになってからのボツに落ち込む横尾は、もがく。横尾が書いてきたのは〈日常的なエンタメ〉で、カジカワなど各社から新作の依頼はあるが、無の状態から書き上げていく作家の仕事はいつも暗中模索だ。横尾と菜種の周りにいる人たちもまた、それぞれに生きているから、仕事上でも私生活でも変化が起こる。「打算的な人」との対決もある。〈利用できるものはとことん利用して、いらなくなったら捨てる〉ような向いている方向がちがう人とは、一緒に歩きづらいとお互いに感じて、遠のく。逆に、大切な人だと思いなおす出来事もある。本書で描かれている、人が人として、それぞれに葛藤している様子はリアルで、読みごたえがある。
近刊の『タクジョ!』シリーズ(実業之日本社)では新人女性タクシー運転手、『君に光射す』(双葉社)では警備員と小学校教師など、小野寺さんの小説は、ある職業に就いている人を書くと「仕事小説」、家族を書くと「家族小説」と言われている。しかし本質的には、本書で菜種が横尾について言うように、〈人を書く作家〉だ。人を書くからこそのディテールや会話の連なりは、小野寺さんの小説の読みどころだと思う。本書であれば、最安の電子レンジを運んで筋肉痛になるとか、ゲリラ豪雨で敷ブトンがずぶ濡れになるとか。一丁三十円の木綿豆腐のエピソードだけで六ページぐらいある。
人の日常は、小さなディテールの連なりだ。嬉しいこともあれば、落ち込んでしまうこともある。木綿豆腐の容器が開けにくくなったというような、ささやかな違和感などもある。日常はすべてその人の私物で、ボツや失恋のような大きな出来事も、小さな出来事も、雨も晴れも、昼も夜も、実はすべてがつながっている。日常は、なんでもないようでいて、変化に富んでいておもしろい。「食っちゃ寝」は人間なら、いや動物なら皆がする営みだが、本書の横尾と菜種の場合は、それに「書く」、あるいは「読む」が、日常の大きなファクターとして加わっている。作家の横尾と編集者の菜種が共有した一年間を確かに描きだし、二人が対になることで生まれた読み心地が、本書のエンタメ性なのだ。
〈作家は、たぶん、二種類に大別される。ほかの何にでもなれたのに作家になるのを選んだ者たちと、作家になるしかなかった者たちだ。/おれはまちがいなく後者。時間はかかったが、それでも運がよかった。作家になるしかなかったのに作家になれなかった人たちはたくさんいるわけだから。/おれは何故小説が好きなのか。/答は簡単。すぐに出る。/文字だけで世界を築けるから。一人でそれができるから〉
横尾と菜種が「今」できるのは、「書く人」、「読む人」であること。立場のちがう二人が一緒に仕事をして作る「小説」とは何だろうか? それは、読者が「読む」ひと時を過ごせる場所。生きていれば、何かしらもがかざるを得ない人たちが、社会から一人で“小脱走”できる場所なのだ。できるだけ多くの人が、自分だけのひと時を過ごせる本になるように、立場も考えもちがう二人がやり取りをする。もがいて、怒りだしたいときもあるだろうけれど、作家は書きだす。出会った編集者と意見を寄せ合い、落としどころを探る。融和で生まれる物語がある。
作家と若手編集者が書くこと、読むことに向き合った一年間を描いたこの小説を、ぜひ読んでみてもらいたい。今いる場所から確実に、脱け出せる物語だから。