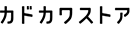あの冬の1か月、たしかに僕らは家族だった。――『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』桜木紫乃 文庫巻末解説【解説:三島有紀子】
レビュー
『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
あの冬の1か月、たしかに僕らは家族だった。――『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』桜木紫乃 文庫巻末解説【解説:三島有紀子】
[レビュアー] カドブン
■舞台で出会った4人の共同生活が、1人の青年の人生を変えてゆく。
『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』桜木紫乃
角川文庫の巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。

あの冬の1か月、たしかに僕らは家族だった。――『俺と師匠とブルーボーイとス…
■『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』文庫巻末解説
解説 桜木さんへの恋文
三島有紀子(映画監督)
桜木紫乃という作家に初めて触れたのは『ラブレス』。2012年のことだ。北海道で「しあわせのパン」という映画をオリジナル脚本で監督、北海道をいろいろ見て回った後だった。北海道にこんな昭和な名前の作家がいるんだなと、読まないといけないような気がしてすぐに読んだ。読み終えた瞬間、自分の中のマグマが激しく動き始めたのを感じ、撮りたいという業が渦巻いた。
主人公の百合江の、壮絶な状況でもからりと受け入れて決断し、執着せず捨てていく姿がたくましく痛ましくも尊く、こんな女性を描きたいと思った。こう書くと成功者の人生が描かれると思われるかもしれない。ちがう。これは、開拓村から始まる北海道の、どこにでもいる名もなき女性の話だと桜木紫乃は語る。厳しい自然と時代の中で「生きる」ために、必死だった。でもその「生きる」ということの底流に何が流れているかというと、それは、愛である。自己へのそれではなく、他者への愛、生き抜くことへの愛であり、人生の最後に百合江には、愛という栄冠が捧げられ讃えられる。サマセット・モームも語っているが、愛されないより愛せないことの方が絶望だと、百合江の人生を通して叩きつけらけた。それはそのまま、桜木紫乃の人間性につながると知ったのは、桜木さんの『硝子の葦』を監督してからだった。
桜木紫乃好きを公言していたら、あるプロデューサーから声をかけられ『硝子の葦』を映像化することになった。映画で『ラブレス』をやりたいと告げると、時代物だからお金がかかるのでまずは『硝子の葦』をやりましょうと言われた。
「一度、きちんと葬ってやった方がいい」。
人生には、一度自分で葬らないといけないことがある。シナハン(シナリオを書くための取材)やロケハン(テーマに即した撮影場所探し)のため釧路を取材して、肌で感じられたのは、家族や小さな頃の関係性を捨てている人も多いということだった。駅の裏側にあるさびれた飲み屋街。のちに桜木さんによくあの飲み屋街を見つけたね、と言われた場所だが、関係性のよくわからない者同士が暮らしているリアルさを感じた。老女と中年の女性の二人は、当然親子だと思っていたら、親子でも同僚でもなかった。老女だけがママとしてこの街を見てきた人だ。他の飲み屋の2階にも、男女関係もないであろう男と女が住み込んでいた。それは、自然の厳しさの中で、寄り添い合いながら生きるしかないという術にも思えたし、それを受け入れる土壌がこの土地にはあるんだと思った。とにかく、カラッと笑いながら、色んな理由で互いに必要としているのがあきらかだった。自分が、本当にどこにも居場所がなくなって、いままでの人生すべてを葬り転がり込むとしたら、北海道にしようと決めた瞬間でもあった。
そして、いよいよ撮影中の現場に現れた桜木さんは、鋭い目で立っていらっしゃったが、とても物腰柔らかで、書くものより明るい印象だった。でも、最初にお会いするのが撮影現場でよかった。私にはやるべきことがある、とハンターみたいな気持ちで現場に立っているのでご挨拶できたが、でなければ緊張して話せなかっただろう。のちに『ベルばら』のオスカル姿に扮装した桜木さんの写真の載った年賀状が届くことになるとは思わなかった頃である。
四回に分けて放送されたドラマの最終回放送後、桜木さんから直接電話が入った。桜木さんは、役者やスタッフの素晴らしさを細かく伝えてくれ、その眼差しには愛が溢れていた。好きな人に、「あなたの描く世界が美しく残酷で好きだ」と言ってもらえた幸せな瞬間だった。映画ではないが、『硝子の葦』は私の代表作のひとつだ。その後、桜木さんに直接お会いできた時に言った。
『ラブレス』をください。
なかなか、『ラブレス』の映画化が進まないうちに、桜木さんの小説は次々と生み出されていく。焦りの中で読み始めた『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』。関係性の説明できない人間たちの家族のような同居生活が描かれ、笑えて笑えて、まさに、ここには釧路のロケハンで見た人たちが生きているではないか。
これが、必要だ。今こそ、現代に生きるすべての人たちに、必要な物語ではないか。
私は、企画書を書き始めた。
『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』企画書 三島有紀子
【イントロダクション】
昭和と呼ばれる、まだ回り道や失敗を許された時代。切ない事情を持ち寄って、不器用な四人が同居生活を始めた。俺(キャバレーの下働き)と師匠(失敗ばかりのマジシャン)とストリッパーとブルーボーイ(シャンソン歌手)。四人が釧路でひととき過ごした時間は、可笑しくて泣けて、生きるために必要な時間だった。【監督ステイトメント】
私がこの本に書かれている登場人物に会ったのは、コロナ禍の前でした。笑って笑って、この四人が愛おしく、状況は苦しくともこんな時間が人生にひとときでもあれば自分の人生にマルをつけることができるなあと感じました。
いま、コロナ禍を経て読み直すと、まるで理想郷のように思えるほど、人間の肉体と生きる力を信じさせてくれます。
それは大人である登場人物が、踊るストリッパー、歌うシンガー、手先と喋りの手品師という、〝肉体〟を駆使して他者をひたすら楽しませるという職業で、世間のルールではなく自分のルールを見つけている魅力が大きいと思われます。
かつて、自分が二十代の頃は、面白い大人がたくさんいたように思うのですが、まさにこの三人がいまの時代に必要ではないでしょうか。
大人の役割は、この世界の面白がり方を伝えること。
日本が明らかに貧しい時代に差し掛かった今、
つらい人生のひとときを、こんな風に笑って生き抜けると信じられる作品を、大人として、世界に発信したいと強く思うようになりました。
何はともあれ「ビバ、人生でございますね」。【あらすじ(のラストだけ抜粋)】
大晦日。年が明けたら三人のショーは終わりとなる。狭いアパートでの四人の同居生活にも終わりを告げ、別れを意味するのだ。
「寒いねえ。ここは北海道だっていうのに、たいした雪も降らない。人間なんてあしたどうなるかなんてさっぱりわかんない。せめて、美味しいもんたくさん食べて、楽しんで暮らしたいわ」シャネルの言葉にみんなが頷いた。「海を見にいきましょう」師匠が言い放った。
「冬の海を見るのも悪くないと思いましてね」
「悪くないわね」とシャネルが答えた。
師匠の(マジック用の)鳩は残り三羽だったが、この日二羽が死んでいた。最後の一羽をポケットに入れて出かける四人。章介(俺)には出掛けに年賀状が届いているのを発見する。生まれて初めての年賀状は母ちゃんからだった。「帯広」の住所が書かれてあった。
「父ちゃん亡くした息子に喪中の未亡人(母ちゃん)が年賀状ねぇ」「ロックだわね」。四人でみた釧路の海は光っていた。「何色に見える?」
真っ黒じゃない?「いや、光っててよく見えない」「そうやな」。
何色かわからない。光っててよく見えない。けれど、それは忘れられない色だ。
四人は、光る海を眺めながら、「オリーブの首飾り」を歌って踊るのだった。そして、師匠、シャネル(ブルーボーイ)、ひとみ(ストリッパー)は、釧路を旅立っていった。章介は、木崎(キャバレーのマネージャー)からこれは分かれ道ではないかと問われる。
「いま、頼る先がないってことは、誰も名倉くんを縛れないってことなんだ。だからいっぺんしっかり恰好良く挫折しなよ。挫折って、自立してないと味わえないことだから」。
一度外に出よう。章介は師匠のように「はあ」と答えながら、そう決めていた。十三年後、章介は東京の小さな映像制作会社で働いている。ある日、老人ホームの余興を撮影して来いと言われやってくる。「人間が多いところっていろんな匂いがするな」。そんなことを呟きながら撮影していると、その余興に登場したのが、年老いた師匠の手品師チャーリーだった。変わらず手品を続けており、以前と同じ失敗をしてしまう。笑う観客。それでも師匠はおどけてみせる。そしてこう話すのだ。
「長い人生、こんなこともありますでしょう。毎度毎度、成功するわけでもございませんですね。これぞ、マジック。ビバ、人生でございますね」
そして「オリーブの首飾り」が聞こえてきた。そんな師匠の姿を、涙しながらカメラにおさめる章介だった。
「師匠…師匠…話したいことが、いっぱいあるんです」。 (おしまい)
なぜブルースをやるのかという問いにブルースの王様B.B.キングは「悲しいことがあるから」と答えたという。桜木さんの作品には、ブルースと名付けられた小説もあり、書かずにはおられない魂の叫びが、自己憐憫を排除した冷静な文章で静かに奏でられていると思う。2024年2月公開となるカルーセル麻紀さんが出演する自分の新作「一月の声に歓びを刻め」を観てくれた人が言った。
「三島さんの作品はブルースなんですね」。
桜木紫乃という作家と、やはりつながっているのだ。
『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』の映画、ドラマ、作りたいと思います。
一緒に、作りませんか。