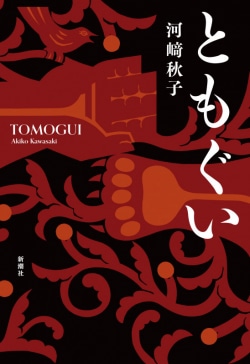『ともぐい』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
熊と人間、その狭間で
人間が生きるための必然のプロセス
角幡 憧れと同時に、僕は熊爪というキャラクターに、特別な思い入れを持って読みました。
河崎 思い入れ、ですか。
角幡 彼は、自分なりの行動倫理に従い自然を相手にするうち、一般常識からどんどん離れていってしまいます。やがて陽子のような不如意な存在に囲まれて、身動きが取れなくなる。その感覚は、普段山や極地に行って活動をしている自分にもよくわかります。結婚して子供ができて、当然家族も未来も自分の思った通りには進まなくなる。行き詰まりを感じることもある。だから、その先で熊爪がどんな道を辿るのか、気になって読み進めました。あの衝撃的な結末は、どの時点で思いつかれたんですか。
河崎 最初から、決めていましたね。
角幡 えっそうなんですか……。ちょっと複雑な気も……。
河崎 なんだかすみません(笑)。狩猟家として美しいクライマックスは熊との対決なのでしょうが、この作品ではそれとは違う答えを出したかったんです。陽子という人間にも向き合い、本意ではないにしろ、受け入れられるギリギリの範囲で、彼女の要望も叶える。二人の接点を探して、あのラストに辿り着きました。
角幡 日露戦争前夜という時代設定も考えられていると思いました。日本が近代国家としての力を高めていく時期であり、人間界と自然界の狭間に身を置く、熊爪のような生き方ができなくなる時期という舞台背景が、作品の世界観をより深いものにしています。
河崎 そこまで読んでいただけるとは……。おっしゃる通り、一般社会から距離を置くことが許されなくなる、時代の変わり目を描きたいと思っていました。
角幡 例えば、物語の序盤で、冬眠しない熊が、様々な問題を起こすじゃないですか。
河崎 阿寒(あかん)からきた「穴持たず」ですね。
角幡 この熊について、熊爪が「阿寒のアイヌの人々が捕えそこなった」と嘆く場面が印象的でした。それはつまり、この作品世界の一昔前には、アイヌの人々が自然との距離を適切にとり、横暴な熊を獲れた時代があったということですよね。さらに熊爪の養父の最期も、一世代前だから許されたものでした。かつては人間と動物の境目が不分明でぐちゃぐちゃと混じり合っていた。だけど近代化の過程でそこが分断され、行き来することすら許されなくなったとき、その狭間で生きる熊爪が辿る運命は非常に示唆的だと感じました。
河崎 ありがとうございます。そのように受け取っていただけて、うれしいです。
角幡 そこに人間らしさの滲む陽子というキャラクターが絡んでくることにも意味がありますよね。人間と自然の境界線が人間の手によって塗りつぶされたように見えました。
河崎 陽子は、熊爪とは対照的に、人間社会に翻弄されてきたキャラクターです。肉体的にはひ弱な、目も不自由な小柄な少女が、山で逞しく生きる熊爪を揺さぶる様子を書きたかった。
角幡 河崎さんも、実際に人間と自然の境界線の変化を感じることはあるんですか。
河崎 例えば札幌では、熊の目撃情報がすごく増えているそうです。ゴミ出しに行ったら出くわしたり……。
角幡 ここ数年の間、それこそ白糠のある道東では、OSO18による被害も深刻でしたよね。結局、ハンターらによって撃ち取られたようですが、彼らのもとには抗議の声がかなり寄せられているとか。
河崎 あのニュースは私もずっと気になっていました。もともと農家側の人間なので、「じゃあどうしたらよかったのか」とも考えてしまいます。
角幡 自然や動物を尊ぶことはもちろん正しい。ただ、そうした言葉は生活と自然が切り離された都市の人々が口にしていることも多いですよね。自らの生命と関係のないところで語られてしまうと、内容が正しくても形式が間違っているような印象を受けます。そういったメッセージを、この作品にも込められているんですか。
河崎 メッセージというほど綺麗なものではないですけれど……。思い出してもらいたい、知らしめたいという気持ちはあったと思います。誰しも動物や植物の体を食べなくてはならない。そのことが忘れられているのではないかと思うことは少なくありません。
角幡 都会のひとが考える「自然保護」や「動物愛護」の中では、動植物を生かすことしか考えておらず、彼らの死が欠落している場合が多いですよね。実際には、彼らの生が人間の生活を脅かしたり、彼らの死によって我々の食が保たれていたりする。
河崎 畜産の世界では、羊などを大きく育てて、子どもを産ませ、産めなくなったら、あるいはオスが生まれたら、肉にして出荷します。それを美味しいと言ってもらうのが、仕事なんです。動物を死なせるために生み育てるという、人間が生きるための必然のプロセスがある。死があるから食が発生する、ということを受け入れなくてはいけないと感じます。
熊という不自由がもたらすもの
角幡 河崎さんにとって熊とはどんな存在ですか。
河崎 北海道において、銃をもってしてもかなわない生き物は熊しかいません。身体的に必ず人間を倒せる存在が、熊です。彼らがいるからこそ、人間には不自由が発生する。それが我々にとっては、実はとても重要なことだと思います。
角幡 不自由さがどこかで必要だということでしょうか。
河崎 もし熊がいなかったら、人間は非常に傲岸な存在になっていたと思うんです。熊がいることで、何かを用心する、何かに備える。自分より上位の生き物がいることを認識するのは、生物としてとても大事なことだし、それによって人間性が豊かになるとも思います。
角幡 熊を恐れる気持ちのおかげで、自然との適切な距離を保つことができる、と。
河崎 そうです。もし熊が絶滅してしまったら、人間はやりたい放題になってしまいますから。
角幡 僕が北極で旅しているエリアでも、白熊には特別な価値があります。地元のイヌイットたちの世界観に沿って言えば「霊力がある」。
河崎 レアな存在ということ?
角幡 希少性というよりは、自然の力や勢いの体現者としての畏怖ですね。河崎さんのおっしゃった通り、彼らは人間に死をもたらす存在なんです。死をもたらす自然、それを体現するのが白熊。
河崎 白熊を狩れることが、人間性の深さを決定づけたりもするのでしょうか。
角幡 その人物がいかに優れたハンターであるかをはかるものさしにはなると思います。みんな「俺は◯歳で白熊を獲った」などと言いますから。
河崎 白熊を獲って一人前になる、という感覚があるのかもしれませんね。
角幡 大地の力を象徴する存在だからこそ、それを狩り、食すことで自然と一体化できる。それは北海道のハンターの方も一緒だと思います。羆を獲りたいという気持ちは、みんなもっているし、僕自身の中にもあります。実は去年、たまたま羆を獲ったんですよ。
河崎 えっ! どちらで。
角幡 道北の天塩です。20メートルくらい先のところにひょっこり姿を現して……。羆についての本はいろいろ読んでいたから、手負いにしてはいけない、絶対に撃ち損じてはいけないと念じながら向き合いました。そんな風に冷静に対処できたのは、北極で白熊と何度も対峙していたからかな。
河崎 羆を撃つときに、白熊と出くわした経験を活かす人もなかなかいない気がしますが……(笑)。
角幡 確かに、僕の場合は特殊かも(笑)。結局、僕は幸運にもその熊を獲ることができましたが、同時にどこか虚しくもあったんです。本当は、熊爪のように、何日も野営して追いかけながら熊を獲りたかった。
河崎 熊を獲ることには、独特の達成感のようなものがありますよね。
角幡 熊爪のように、特定の個体と因縁の関係を結んで追いかけ合うなんて、ものすごく憧れます。
河崎 ただ、狩猟者としての熊爪の欲求は単純なものだとも思います。熊は、鹿を襲うときに「殺そう」とは思わないですよね。熊爪も、それと同じように、獲った、得た、くらいの純粋な気持ちだと思うんです。彼は自分が人間よりも熊に近い存在だという自己認識がありますし。
角幡 確かに狩猟をしていると、「殺した」ではなく「獲った」という気持ちになりますね。
河崎 畜産をしていた頃、時間をかけて手入れをした牧草地で、羊や牛がおいしそうに草をはんでいるのを見ると、とても満たされた気持ちになりました。これが見たくて、頑張ってるんだよ、と。
角幡 熊爪が熊や鹿を獲るときも、それと同じくらいシンプルな満足感があるのかもしれません。