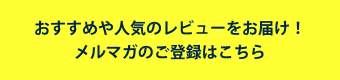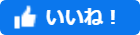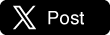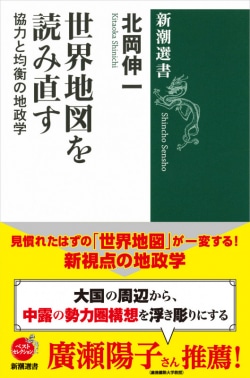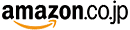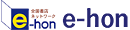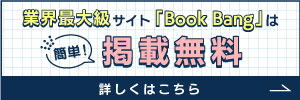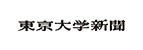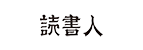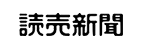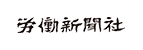『世界地図を読み直す』
書籍情報:JPO出版情報登録センター
※書籍情報の無断転載を禁じます
【筆者対談】北岡伸一×池内恵/「大国の周縁」から見た地政学
[文] 新潮社

2018年9月にアメリカ・ニューヨークで開かれた国連総会の様子(Wikimedia Commonsより)
「日本は小国の話にしっかり耳を傾ける義務がある」――この度、『世界地図を読み直す:協力と均衡の地政学』(新潮選書)を刊行した北岡伸一・国際協力機構(JICA)理事長と、中東・イスラーム研究者の池内恵・東京大学教授が、日本外交の要諦について対談しました。
***
池内 序章ではまず海洋国家的な「自由で開かれたインド太平洋構想」について書かれていますね。私のような中東研究者ですと、地政学はもっぱら海上権力(シーパワー)を中心に考えます。スエズ運河、バーブ・エル・マンデブ海峡、ホルムズ海峡といったチョークポイント(海上水路の要衝)をどう押さえるか、海上権力の大国が最重要視したことによって「地域」と認識されるようになったのが近代の中東です。

池内恵氏
北岡 スエズ運河と、それを管理するエジプトは、日本にとって非常に大切です。本でも書いたように、私もJICA理事長としてエジプト大統領と二度会談し、初等教育への協力を実施しています。
紅海の入口であるバーブ・エル・マンデブ海峡について言えば、エリトリア情勢に注目する必要があります。エチオピアとの紛争が沈静化すれば、いま各国が拠点を置いている隣国ジブチよりも、エリトリアの方が重要になるかも知れない。
ホルムズ海峡も、日本が石油を確保するための生命線です。ただシェールオイルやその他のエネルギー革命によって、その状況が変わる可能性もあります。
池内 日本ではお役所でも大学でも「主流派」と目される人々は、どうしても経験や視野が欧米に偏りがちです。それだけに、北岡先生が中東やアフリカの国々をご自身で回って、その重要性を本に書いて下さるのは、とてもありがたいです。これらの地域に注目するようになったのは、やはり国連大使を経験されたことが大きいのでしょうか。
北岡 国連の選挙では一国一票ですからね。ただ、そのような打算を抜きにして、真剣に課題に取り組んでいる国には、国力の大小に関係なく、きちんと目配りする義務があると感じてきました。
国連総会では、大国の首脳がスピーチすると、各国の大使が舞台裏にずらっと並んで、「いや、素晴らしい挨拶でした」とかやるわけです。これが小国の首脳の場合だとほんの数人しか待っていない。私は小国の時でもできる限り行くようにしていました。日本は十九世紀以降、西洋中心の国際社会の中に入っていき、世界有数の先進国になった。そのような経験を積んだ日本には、同じ道を目指そうという小国の話にしっかり耳を傾ける義務があるような気がするんです。
※【筆者対談】北岡伸一×池内恵/「大国の周縁」から見た地政学「波」2019年6月号より
***
北岡伸一(きたおか・しんいち)
1948年、奈良県生まれ。東京大学名誉教授。2015年より国際協力機構(JICA)理事長。東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科博士課程修了(法学博士)。立教大学教授、東京大学教授、国連大使(国連代表部次席代表)、国際大学学長等を歴任。2011年、紫綬褒章受章。著書に『清沢洌』(サントリー学芸賞受賞)、『日米関係のリアリズム』(読売論壇賞受賞)、『自民党』(吉野作造賞受賞)、『国連の政治力学』、『外交的思考』など。
池内恵(いけうち・さとし)
1973年、東京都生まれ。東京大学先端科学技術研究センター教授。東京大学文学部イスラム学科卒業。同大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。著書に『現代アラブの社会思想』(大佛次郎論壇賞)、『書物の運命』(毎日書評賞)、『イスラーム世界の論じ方』(サントリー学芸賞)、『イスラーム国の衝撃』(毎日出版文化賞特別賞)、『中東 危機の震源を読む』、『サイクス=ピコ協定 百年の呪縛』『シーア派とスンニ派シーア派とスンニ派』などがある。