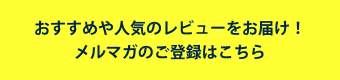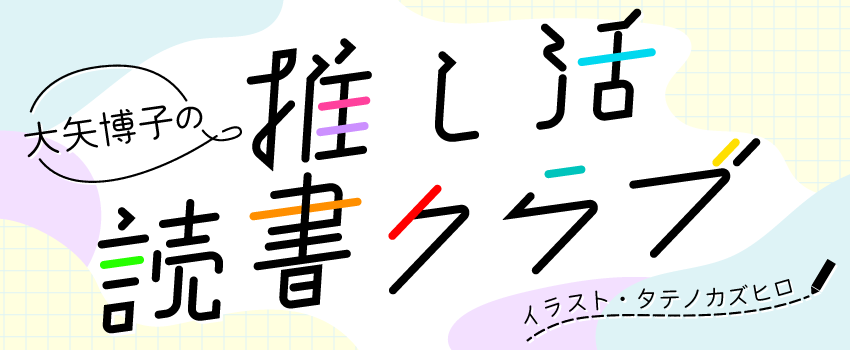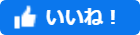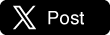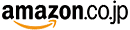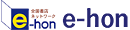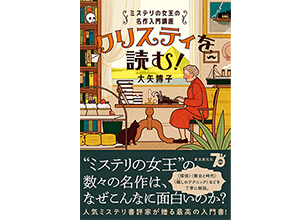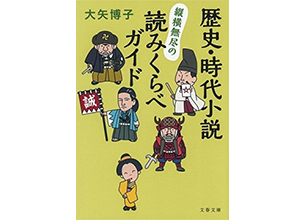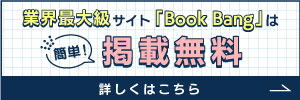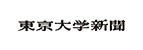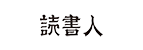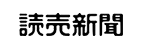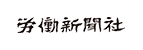福士蒼汰、松本まりか主演「湖の女たち」グロテスクな人間の業を重層的に描いた小説をよくぞまとめた! チャレンジングな役に挑んだ俳優たちと琵琶湖の美しさにゾクゾク
推しが演じるあの役は、原作ではどんなふうに描かれてる? ドラマや映画の原作小説を紹介するこのコラム、今回は見終わったあとも心にずっしり残るこの映画だ!
■福士蒼汰、松本まりか・主演!「湖の女たち」(東京テアトル、ヨアケ・2024)
-
- 湖の女たち
- 価格:825円(税込)
本屋大賞を受賞した宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』(新潮社)で描かれた琵琶湖は明るくて親しみやすくて、青春と郷土愛を載せたミシガン号が気持ちよく水面を進む印象だった。けれど『湖の女たち』で描かれる琵琶湖は違う。そこにあるのは圧倒的な美しさと厳しさ、そして人間たちが何をしても泰然としてそこにある「冷酷な揺るぎなさ」の象徴だった。
原作は吉田修一の同名小説『湖の女たち』(新潮文庫)。琵琶湖の近くにある介護施設で100歳の入居者・市島民男が死亡した。人工呼吸器が止まっているのにアラームが鳴らなかったことを不審に思った遺族が通報、殺人事件として捜査が始まる。施設を訪れた刑事の濱中圭介は介護士の聴取を行う中、豊田佳代という介護士に興味を抱く。それは容疑者としてではなく、歪んだ支配対象としてだった。
濱中は上司の伊佐美とともに介護士の松本郁子を疑い、苛烈な取り調べを進める一方で、豊田へのアプローチを始める。出産間近の妻がいる身でありながら豊田を深夜に呼び出し、サディスティックな欲求をぶつけるようになる。濱中を恐れながらも、豊田は彼の言いなりになることに快感を見出していく。
その頃、週刊誌の記者・池田はかつてこの地で起きた血液製剤の薬害事件を取材していた。大勢の犠牲者を出した薬害にもかかわらず大物政治家の圧力で立件が見送られたのだ。池田はその薬害に介護施設で殺された市島がかかわっていた可能性に気づく。そして関係者たちの共通点を戦時中の満州に見つけるが……。
というのが原作と映画両方に共通する導入部だが、こうしてざっくりまとめただけでも、介護施設での殺人事件、刑事と聴取対象者のインモラルな関係、薬害事件、満州での軍の行動、政治的圧力などなど、それだけで映画が一本作れそうなほどの大きな柱がいくつもある。さらに、容疑者とされた松本は明らかにスケープゴートで、警察による組織的な冤罪づくりというもうひとつの大きな柱もある。つまり、盛りだくさんなのである。
これだけのおぞましい出来事が並行して語られれば散漫になりそうなものなのに、原作も映画もそうなっていないのがすごい。それには理由があるのだが、それは後述。まずはいつものように原作と映画の違いを紹介していこう。

イラスト・タテノカズヒロ
■チャレンジングな役柄に挑んだ俳優たちがすごい!
映画の流れは原作に極めて忠実だ。これほどの重層的な構造の小説を、よくぞ構成要素を削ることなく140分に収めたなあと驚いた。違うのは原作では男性だった週刊誌記者・池田が映画では女性(福地桃子)になっていたこと、その取材の手順が一部カットされていたこと、豊田の恋人の存在や妄想シーンがカットされていたことくらいである。
逆に、原作にはないシーンが冒頭に加えられていた。夜明けの琵琶湖で濱中(福士蒼汰)が釣りをしている場面から始まるのは原作も映画も同じなのだが、映画ではその近くに、施設の仕事の休憩時間を利用して湖を訪れた豊田(松本まりか)の車が停まっている。その中で豊田はひとりで、その、まあ、なんつーか、秘め事というか、そういうことをしている。豊田は気づいていないが、それを濱中が(多分)見ている──というシーンから映画が始まるのだ。
いきなりだな!と思ったが、この場面が加えられたことで、施設で豊田と再会した(豊田にとっては初対面)濱中が彼女に性的な興味を持ったことが「わかりやすく」なった。しかも「釣る男」と「釣り上げられる女」という関係の暗示にもなっているのだ。なるほどなあ。──ところで、このタイミングで豊田が施設を出ているということは、彼女にはアリバイがないってことになるんだが、それはいいのかな?
とにもかくにも、このふたりのお芝居がすごかった! 福士さんの嗜虐性と、松本さんの危うさ。小説では濱中の内面はあまり描写されず(家庭や仕事については内面描写もあるが、豊田との関係については何を考えているのか説明は少ない)、そのわけのわからなさが醸し出す怖さがそのままスクリーンに出ていた。逆に豊田の思考や迷いは原作では丁寧に言葉を尽くして描写されるが、映画の豊田はそんな説明はしない。表情や動き、声音だけで表現した松本さんホントすごい。ふたりの関係は倒錯しすぎていて理解も共感もなかなかできないのだが、それでも映画のふたりを見ていると、わからないなりにも「こういうこともあるのかもしれない」と感じられたのだ。
そのふたり以上に鮮烈だったのが、濱中の上司・伊佐美を演じた浅野忠信さん! 過去に懸命に捜査した事件が圧力で潰され、それ以降やさぐれてしまったのか何なのか、冤罪上等とでもいうような捜査をする。でもその一方で記者に情報を流してやったりもして、完全に荒み切ったわけではない。むしろ今の自分が嫌で、でもどうしようもないという伊佐美の閉塞感が痛いくらいに伝わってくる。終盤で彼が口にする「世界は美しいんか?」という一言には「うわあ」とのけぞるくらいゾクゾクした。
■グロテスクな人間を冷徹に見つめる自然の描写
ストーリーも構成も映画は原作通りで、小説のテーマもそのまま完璧にすくいあげられていた。多くの要素を持った群像劇のような構造でありながらとっちらかった印象を与えないのは、どのエピソードも、同じテーマに収斂していくからだ。
原作にしろ映画にしろ、読者/観客はここに描かれる出来事の中に、現実の事件がモデルになったものが複数あることに気づくだろう。血液製剤の薬害事件が最たるものだが、冤罪のくだりも看護助手に嘘の自白を強要した現実の冤罪事件を思い出す。また、実際に起きた大量殺人事件を想起させるニュースも作中に登場する。戦時中に満州で行われていた出来事も史実。そして、小説でも映画でも、与党の女性政治家が「子どもを産まないLGBTの人には生産性がない」と発言したという話が紹介され、これが物語の通奏低音となる。
どれもこれもおぞましい話で、しかもそれが現実に起きていることだと思うとおぞましさは2倍増し。そりゃ伊佐美もやさぐれるわ。戦時中の話と現在の話を重ねることで、人間はそのおぞましさを世代を超えて受け継いでいるのだと暗澹たる気持ちになる。そして、100歳の老人を介護する/殺すという行為も、命を顧みない戦争も薬害も、必死の捜査や取材が「上」の圧力でなかったことにされるのも、殺人事件の真相も、すべて「生産性」という同じところに行き着く。この物語は「生産性とは何か」をとことんおぞましい、グロテスクな人間の業として描いているのである。
そんな中、唯一モデルが存在しない、独立したエピソードとして描かれるのが濱中と豊田のインモラルな関係だ。生産性という点でいえば、ふたりの関係は物理的にも精神的にも何も生み出さない、どこへもつながらない関係である。だが、生産性も社会もまったく眼中になく、ただ自らの欲望だけで堕ちていくふたりは、そのグロテスクな世界の中にあって最も「生きている」ような気がしたのだった。
人間のグロテスクさの対比として描かれる琵琶湖の、あるいは満州の平房湖の、なんと美しいことか。伊佐美の「世界は美しいんか?」という呟きに答えるように、物語は冷酷なまでに美しい湖の姿を描き出す。映画の映像も素晴らしいが、それを文章のみで綴った原作も素晴らしいのでぜひお読みいただきたい。この奇跡のような美しい自然の中で、この湖に冷徹に見つめられて、人間はいつまで自分をグロテスクなままにしておくつもりだろう。
大矢博子
書評家。著書に『クリスティを読む! ミステリの女王の名作入門講座』(東京創元社)、『歴史・時代小説 縦横無尽の読みくらべガイド』(文春文庫)、『読み出したらとまらない! 女子ミステリーマストリード100』(日経文芸文庫)など。名古屋を拠点にラジオでのブックナビゲーターや読書会主催などの活動もしている。
連載記事
- 杏・主演「かくしごと」よくぞここまで原作通りに……、からのラストシーンの改変にびっくり! 「映画の続きを原作で」という珍しい関係性をみた 2024/06/19
- 山崎賢人・主演「陰陽師0」映画オリジナルストーリーだが、まごうかたなき「原作小説の前日譚」! 映画を観ると原作がさらに面白く 2024/05/08
- 岡田将生・羽村仁成主演「ゴールド・ボーイ」中国から沖縄に舞台を変えた映画版 衝撃のサプライズをぜひ原作で! 2024/03/27
- 杉咲花、志尊淳主演「52ヘルツのクジラたち」顔がグズグズになるくらい泣いた! 原作を完璧に再現した映画版 あえての改変シーンの理由を考察 2024/03/13
- 土屋太鳳、佐久間大介、金子ノブアキ出演「マッチング」「あのパターンね」からの「はああっ!?」 気持ちよく騙された! 小説も書いた監督がそれぞれに込めた思いとは 2024/02/28
- 松村北斗・上白石萌音主演「夜明けのすべて」原作とは大きく展開が違う映画版 上白石も「原作を読んでほしい。読んで、観て完結」 2024/02/14
- 重岡大毅主演「ある閉ざされた雪の山荘で」あのミステリをどうやって? 小説ならではの大仕掛けをこう変えたか! 映像ならではの面白さも解説 2024/01/24
- 亀梨和也主演「怪物の木こり」結末が原作と違う! でもこの改変はいい! サイコパスの主人公はどう変わったのか 2023/12/13
- 稲垣吾郎、新垣結衣主演「正欲」価値観をぐちゃぐちゃにかき回される物語 映画ではカットされた圧巻のシーンをぜひ原作で! 2023/11/29
- 永瀬廉主演「法廷遊戯」理の原作と情の映画 お互いを補完しあう理想的なメディアミックス! 2023/11/22