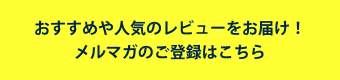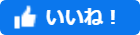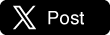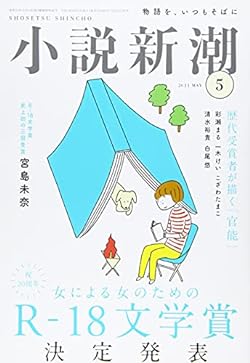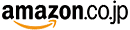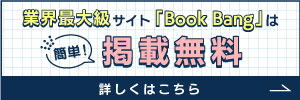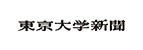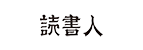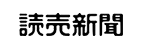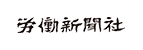「本屋大賞」受賞者の町田そのこさんは、R-18文学賞出身。写真は第15回R-18文学賞の受賞者(左から)笹井都和古さん、町田そのこさん、一木けいさん(撮影・新潮社)
「女による女のためのR-18文学賞」、通称「R-18文学賞」でデビューした作家たちの勢いがとまらない。今年、『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞した町田そのこ氏(第15回受賞者)をはじめ、直木賞候補に名を連ねる窪美澄氏(第8回受賞者)や彩瀬まる氏(第9回受賞者)もこの賞の出身だ。
20年前、女性編集者の手弁当からスタートした同賞は、数ある新人賞の中でも独自の存在感を発揮。活躍する女性の書き手を次々に世に送り出してきた。
創設時から見守ってきた書評家の吉田伸子氏に、その秘密と魅力を解き明かしてもらった。

R-18文学賞
「女性のための官能」が読みたい!
女による女のためのR-18文学賞(以下、R-18文学賞)が創設されてから、もう20年が経つのか――。文字通り、手弁当で始まった(んですよ!)この賞の立ち上がりから見てきた身としては、めちゃくちゃ感慨深いものがある。
20年といえば、生まれた子どもが成人式を迎え、アラフォーだった私がアラカンになる、それほどの年月である。なにはともあれ、この賞を立ち上げ、今日まで大事に育ててきたKさんとSさんに、最大級の敬意と感謝を送りたい。
もうね、この賞の創設に至るまでの道のりは、まんま「プロジェクトX」なんですよ。そもそも、編集者が文学賞を立ち上げる、ということがどれだけ異例なことであったのか。しかも、募集する側も応募する側も選考する側も、全て女性、という縛り付きで、である。そこにあったのは、小説を愛してやまない二人の“想い”である。その“想い”は、R-18文学賞のサイトにも書かれてある。
R-18文学賞は、賞の創設10年にして、募集作品の内容を「女性が書く、性をテーマにした小説」から、「女性ならではの感性を生かした小説」に変更したのだが、そこにはこう書かれている。
――賞が設立された10年前、小説に描かれる官能は主に男性のためのものであって、女性が性を書くことはタブーとはされないまでも、大変な勇気がいることだったと思います――
だから、「性をテーマにすえた新人賞」として、R-18文学賞はスタートしたのだ。そう、今から20年前、官能は「主に男性のためのもの」だったんですよ、みなさま! いや、本当に。乱暴に言ってしまえば、「嫌よ嫌よも好きのうち系」とか「一見貞淑な女子が実はニンフォマニア系」とか、女性からしたら「あ?(めっちゃ平坦声)」というものが大半を占めていたのだ。もちろん、書き手は男性。
違う! 全然違う! 私たちが読みたい「官能」は、こうじゃない! 物語で描いて欲しいのは、それじゃない!
小説を愛し、小説の力を信じているKさんとSさんの、そんな心の声が結実したのが、R-18文学賞なのだ。
ちなみに、女性が読みたい「官能」と言っても、それは十人十色。私が読みたい「官能」とあなたが読みたい「官能」は違っていて当たり前だ。みんなちがって、みんないい、のである。けれど、少なくともそれは、男性の願望充足のためのそれではないし、妄想充足のためのそれでも、ない。むしろ、女性の願望充足であっていいし、妄想充足であっていい。だって、それまでは、「男性のための官能」しかなかったのだから。
個人的なことを書くならば、私が、R-18文学賞受賞作が世に出るよりもはるか昔に、ぐっときた「官能」は、山田詠美さんが描いたこんなシーン。情事の後、二人で食事をしていた時のこと。具体的に二人が何を食べていたのかは覚えていないけれど、手掴みでその料理を食べていた(と思う)男が、自分の指を嗅いで「smell like yours」と言うのである。詠美さん、なんてことを! と、どきどきしながらも、そうだよ、こう言うことだよ、「官能」って! と思ったことを今でも覚えている。
現代作家の充実の一翼
R-18文学賞は、その「女性が書く、性をテーマにした小説」で募集された十年間が第一期。「女性ならではの感性を生かした小説」で募集されている現在までが第二期だ。選考委員は第一回が光野桃さんと山本文緒さん、第二回から第五回が角田光代さんと山本文緒さんで、第六回から第十回までは、そこに唯川恵さんが加わる(第五回のみ角田光代さん単独)。第二期となる第十一回からは、辻村深月さんと三浦しをんさんで、第十四回からは、「友近賞」の新設に伴い、タレントの友近さんが加わって現在に至る。
R-18文学賞の特色の一つに、「大賞」の他に「読者賞」を設けていることがある。R-18文学賞のサイトには、こう書かれている。「書くことはできないけれど、読むのは大好き、という読者のために『読者賞』を設けました。Web上で最終候補作品を公開し、女性読者限定で感想コメントを募集します」つまり、読者からの支持が最も多かった作品が、「読者賞」となるのだ。こういうところにも、この賞の公平さというか、書き手、読み手、双方の女性をとりこぼさないようにしよう、という懐の深さがあらわれている。ちなみに、過去に大賞と読者賞のダブル受賞をした作品は、吉川トリコさんの「ねむりひめ」、宮木あや子さんの「花宵道中」、白尾悠さんの「アクロス・ザ・ユニバース」の三作しかない。
それにしても、と思う。今、手元に資料として、歴代のR-18文学賞受賞者のリストがあるのだけど、なんとまぁ、現在の女性作家の充実の一翼となっていることか。第一期の受賞者には、前述の吉川トリコさん、宮木あや子さんをはじめ、直木賞候補となった窪美澄さん、彩瀬まるさんがいる。デビュー作や、その後に書いた作品が映像化されている方も、窪さん、宮木さん、吉川さん、山内マリコさん、蛭田亜紗子さん、と多数。
第二期の受賞者の顔ぶれも錚々たるもので、小林早代子さん、町田そのこさん、一木けいさん、夏樹玲奈さん、清水裕貴さんと、次代を担う書き手の方たちがずらりと並んでいる。もちろん、ここに名前を挙げた方だけに限らない。R-18文学賞を受賞された方たちには、個人的には等しく思い入れがある。
でも、だからこそ。受賞後にまだデビューを果たしていない方たちのことも気になってしまう。R-18文学賞は短編の賞なので、受賞したとしても、その一作だけでは単行本にできるボリュウムにならない。少なくともあと四篇か五篇書かないと、一冊にまとめることは難しいのだ。難しいというか、無理、なのである(受賞作だけ、で電子書籍になっている方もいますが、ここでは単行本としてのことです)。
次作に編集者さんのOKがなかなかもらえない(ダメ出しをされる)ことを繰り返していくうちに、気持が挫けてしまうこともあったかもしれない。たとえば家族に介護が必要になったりとか、何らかの家庭の事情で、物理的に執筆の時間が取れなくなってしまったのかもしれない。可能性はかなり低いけれど、受賞「だけ」で満足してしまったのかもしれない。理由は一つだけではなくて、複合的にいくつも重なっているのかもしれない。
けれど。そういう受賞者の方にこそ、伝えたい。大丈夫、あなたは書ける、と。書きたい、書こうという気持が心の奥にある限り、あなたは書ける、と。なぜならば、あなたは、R-18文学賞の受賞者なのだから。数多の作品の中から選ばれたのが、あなたの作品だったのだから。唯一無二の、あなたの作品だったのだから。蛹になるのに時間がかかっていたり、蛹でいる時間が長かったりしているだけなのだから、大丈夫。自分を信じてください、と。
万に一つ、もしかしたら、そういう方にとっては、R-18文学賞の受賞が、ただ今は十字架になっているのかもしれない。けれど、そんな時は、心の底からその十字架を背負うことを渇望し、けれど背負えなかった人たちが、自分の受賞の陰にはいるのだということを、ほんの一瞬でもいいので、思ってみてください。背負えなかったひとたちの涙を思ってみてください。大丈夫、あなたは書ける。
賞を支持する人たちの熱い想い
今回、この原稿を書くにあたって、新潮社の「女による女のためのR-18文学賞」のサイトを読んで、気づいたのだが、受賞作を含む最終候補作への、選考委員の選評が、本当に素晴らしい。第一期の光野さん、角田さん、山本さん、唯川さん、第二期の辻村さん、三浦さん。光野さん以外の方が、全員直木賞作家であるということも凄いけれど、選考委員がここまで詳しく候補作を読み解いて、長所も短所もきちんと指摘してくれるという点では、数多ある新人賞のなかでも、このR-18文学賞が一番なのではないか。
この選評は、R-18文学賞に応募した人、応募を目指す人だけに限らず、作家を目指す全ての人に、一度熟読してもらうことを、強く強くお勧めします。とりわけ、第二期から選考委員となった三浦さんの、個別の選評に入る前振りというか、総論は、そのまま小説論として読んでも勉強になる、と思います。
自身も書き手として多忙な選考委員の方々がここまで肩入れしている(と思う!)のは、そもそものR-18文学賞の創設理由に起因していると思うし、男性作家に比べると、まだまだ数が少ない女性作家を増やしたい、だから女性作家の卵たちを応援したい、という思いがそこにあるからではないか、と思う。もちろん、Kさん、Sさんの“意気”に加勢したい、という想いも。
今でこそ、女性編集者は各社で確実に増えているけれど(そして、彼女たちはめちゃくちゃ優秀である)、R-18文学賞が生まれた20年前は、女性誌の編集部はまだしも、文芸部署の女性編集者は、男性と比べて格段に少なかった。その文芸部署で仕事をしていくうえで、KさんもSさんも、本来なら負う必要のない辛さや理不尽さを、女性であるがゆえに、何度も味わってきたはずだ。だから、せめて、物語の世界では、その状態を変えていきたい、と思ったのではないか。その端緒として、女性が描く、女性のための「性」があったのではないか。
出版界は比較的男女差が少ないと思われているし、事実異業種と比べれば、そうだとも思う。でもですね、いわゆる大手や老舗出版社の現社長、みんな男性なんですよ、21世紀の現在でさえ。今や一世を風靡した感のある「鬼滅の刃」の作者・吾峠呼世晴さんが女性だと知った時、「あぁ、週刊少年ジャンプの女性の連載作品が、一世を風靡するまでになるとは!」と一人胸熱になっていた私ですが、「週刊少年ジャンプ」の編集長が女性になったら、その時はお赤飯を炊こうと思っています。
と、ちょっと話が横道にそれましたが、R-18文学賞は、この先も続いて行って欲しいし、続いていくべき賞である、と思う。女による女のためのR-18文学賞よ、永遠なれ!

R-18文学賞・歴代受賞者

R-18文学賞・歴代受賞者
株式会社新潮社「小説新潮」のご案内
http://www.shinchosha.co.jp/shoushin/
現代小説、時代小説、ミステリー、恋愛、官能……。ジャンルにこだわらず、クオリティの高い、心を揺り動かされる小説を掲載しています。
小説と並ぶ両輪が、エッセイと豊富な読物です。小説新潮では、毎号、ボリュームのある情報特集や作家特集を用意しています。読み応えは新書一冊分。誰かに教えたくなる情報が、きっとあります。
【購読のお申し込みは】
https://www.shinchosha.co.jp/magazines/teiki.html
関連ニュース
-
戦争に勝つために必要な「ふたつの目」とは――塩野七生 読者との対話2
[イベントレポート](歴史・時代小説/世界史)
2019/02/05 -
オリコン2017年上半期“本”ランキング 1位に村上春樹『騎士団長殺し』
[文学賞・賞](日本の小説・詩集)
2017/06/01 -
ピース又吉の新作『劇場』が初登場で総合1位を獲得 30万部スタートで更に増刷も【文芸書ベストセラー】
[ニュース](日本の小説・詩集)
2017/05/20 -
次は『夫のトリセツ』 ベストセラー『妻のトリセツ』待望の夫編が刊行
[ニュース](タレント本/家事・生活/心理学/演劇・舞台)
2019/11/02 -
「死刑はやむを得ないが、私としては、君には出来るだけ長く生きてもらいたい」裁判官の言葉が沁みる…… 2007年から売れ続けるロングセラー新書がベストセラー1位に
[ニュース](日本史/事件・犯罪)
2023/05/20